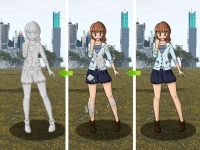「状況はどう?」
ミオとラビスの戦闘現場に着いたシグーネは、ずっと様子を見守っている青髪の少女……セイナに声を掛けた。
「あ、シグーネさん? まだ……これといった決め手はないけど、ミオちゃんの方が押されている。」
「そうか……」
シグーネとプウーペが到着しても、まったくそれに気づかず戦いを続けているミオとラビス。
「こんな戦い、まったくもって時間の無駄だ。早くアジトへ戻って、先日完成したばかりのカラオケルームで、ワラワは『マイ・ウェイ』を熱唱せねばならん!」
戦いなから、唐突に妙な事を口走るラビス。それを耳にしたプウーペは、
――また、アジトにそんな物を作ったのですカ? いつもながら、ラビス様は……。―
と、呆れた表情。
「神楽巫緒よ……。そんな訳で、さっさと終わりにしてやる!」
ラビスはそう言って、ベルトに備えてあった小さな杖を取り出した。
「ダーク・メタモルフォーゼ!」
ラビスが手にする杖から放たれる怪しい光。必死で飛び避けたミオだが、そのためその光は、周りに集まっている野次馬の一人である、まるでモデルのような美しいボディーラインのOLらしき女性に当たってしまった。
「いや、なによ……これ!?」
光が女性の全身を覆いつくすと、徐々に……徐々に女性の姿が変貌し始めていく。
切れ長の目はつぶらな丸い目となり、高い鼻……厚めの色っぽい唇は合体したように一つとなり、尖った嘴に変わる。長い脚は短く、細い腕は平たく大きく……翼と変わる。
そして本人にとって最も屈辱であろう、ボンッ!キュッ!ボンッ!のくびれたボディ!
「やだ、あたしのナイスバディ―が……!?」
細いウエストは太く丸く。自慢のFカップはストンと平ら、そう……そのものズバリの『鳩胸』に!
「クルッ…クルッ!」
なんと、あの美しい若きOLは、どこにでも居そうな一羽の鳩となってしまったのだ!

「は……鳩に、変わった……!?」
予想もしなかったラビスの術に、ミオもセイナもあまりの驚愕で目が釘付けとなる。
「変化は動物だけではないぞ。」
そう言うラビスの持つ杖から、再び光が放たれる。必死に光を飛び避けるミオ。
それは、またしても野次馬の一人、十代後半くらいの少女に当たった。
実は彼女、あの有名なアイドルユニット……『OKF48.5』、チームK所属の野村咲夜(のむらさくや)であった。レッスン帰りに人混みを見つけ、そのまま一緒に見物してたが、まさか自分に変身光線が当たってしまうとは!?
全身が光に包まれると、まるで前後から見えない壁に挟まれていくかのように、彼女の身体はゆっくり……ゆっくり、ぎゅ~~っ!と押し潰されていく。もう、その厚さは1㎝にも満たないだろう。だが、そこで終わりではない。
今度は頭の先と爪先を見えない手に摘まれたかのように、上下にグィ~~ンと引っ張られ、同様に両脇を左右に引っ張られると、一気に放された。
それはまるで、引っ張ったゴムを手放すと反動でバチ~~ンッ!と縮むように、彼女の身体も一気に縮む。
これを10回程繰り返された彼女の身体は、幅2cm…長さ10cm程の小さな薄い板状に。それはまさに、一枚の『チューインガム』。

「こ、こんどは女の子が……ガムみたいに!?」
新たな少女の変化に、またしても釘付けになるミオ。
「ワラワの変化の術は、人間以外の物なら何でも変化させることができる。動物であろうと物品であろうと、そして食品であろうと……な!」
まるで少女の変化を楽しんだように、ラビスは冷やかな笑みを浮かべていた。
そうこう言っていると、ガムになった咲夜に一陣の風が舞い込んだ。咲夜はその風に乗って宙を漂うと、戦いを傍観していたシグーネの足元にポトリと落ちた。
「あら、ガムになった女の子。ふ~ん、アタシに食べてもらいたいのかしら?」
シグーネはガムを拾うと、ニヤリと微笑む。
もちろんガムになったとはいえ、咲夜自身が食べられたいなんて願っているはずは無い。
だがシグーネは、食材となった女の子は全て自分に食べられたいと思っている……なんて、都合の良い解釈ができる女だ。
「それじゃ、いただくとするわ!」
手にしたガムを嬉しそうに口の中に放り込む。
シグーネの歯がムシャ…ムシャ…と噛みしめる度に、咲夜は……、
「きぅ……」「ぷぴぃ……」と、可笑しな奇声をあげ続けた。
だが、笑わないでほしい。ガムとなった彼女は、頭部も脚も皮膚も神経も……、全てが統一化している。つまり全身が神経であり筋肉であり、そして性感帯でもある。
噛まれることで全身が刺激され、今まで体験したことのないエクスタシィを感じていたに他ならない。
それによって、ガムと化したその身体からは香りや体液だけでなく、人気アイドルとして口にするのも恥ずかしいような汁も、多少放出していたようだ。
「ふ~ん! この子……見た目は随分カワイコぶっていたけど、結構……下品な味もするのね! でも、それがいい♪」
そう言いながら更にクチャクチャと噛み締め、十分なほど咲夜ガムを味わうシグーネ。
しばらくして、隣で戦闘を見守っているセイナに向かって、
「ちょっと、手を出して~!」と声をかけた。
セイナは言われた通り手を差し伸べると、なんと……シグーネは、噛み続けていた咲夜ガムを「プッ!」と、その手に吐き出したのだ。
「な、な、な、何するんですかぁ~っ!汚いーっ!!」
思わず手を振り、グニャグニャのガムを払い落とそうとするセイナ。
「捨てたら駄目よ! そんな形(なり)だけど、その子……まだ生きているからね。」
「えっ!?」
シグーネの言葉に、改めて噛み潰れたガムを見直すセイナ。
残骸としか思えない噛み潰されたガムではあるが、よく見ると……微かに鼓動のようなものが聞こえ、表面では目らしきものがグルグルと回っている。そう、こんな状態でも咲夜はまだ生きているのだ!?
「ホント……です。この人……まだ生きている?」
「ラビスの闇の力が衰えさえすれば、その子たちはアンタたち人魚の術で、元に戻す事ができるわ。だからそれまで、しっかり保護してあげなさい!」
なんか、上手いこと言いくるめられたような気がしないでもないが、
「わかりました!」
セイナは素直にそう言うと、吐き出された咲夜ガムを自分のハンカチで包むと、やさしく握りしめた。
「さて、次はどいつが物や動物に変化するかな?」
対戦相手であるミオよりも、周りで見物している群衆に杖を向け、ラビスはニヤリと冷笑する。
「こ…これ以上、罪の無い人に手を出させはしない!!」
そう叫んだミオは、右掌を伸ばしラビスへ向けた。
「くらえぇぇぇぇっ!! ホーリー・ライトぉぉっ!!」
伸ばした右掌から眩い光が広がると、それは一気に真っ白な光の束となって放たれた!
――ラビスの魔法属性は『闇』! その闇属性に有効なのは、『光』属性……!!―
そう、ミオが新たに放った魔法は、闇属性に最も効果の高い、光属性魔法。
「ほぅ!? さすがはウィンディーの娘、神楽巫緒。母同様……光でワラワを封じ込める気か。だが……」
ラビスは自身も左手を長々と伸ばし、その掌から紫色で半透明の壁を繰り出した。壁はミオが放つ光属性魔法を軽々と受け止める。
「お前の母……ウィンディーの光の術ですら、ワラワの闇魔力に歯が立たず、結局……増幅装置まで引っ張り出して、やっとワラワを封じ込めることができたと言うのに。なのに、お前ごときの魔力で、ワラワに敵うと思っておるのか?」
ラビスの言葉通り、ミオ……渾身のホーリー・ライトは、ラビスの繰り出した壁に遮られたままだ。
「シグーネさん、ミオちゃんの魔法はラビスを打ち破れそう?」
ミオとラビスの攻防を心配そうに見守りながら、シグーネに問いかけるセイナ。
その問いにシグーネは、
「ラビスの属性は闇。そしてミオが今……放っているのは、光属性魔法。属性だけで見ればミオの方が有利だけど、それはあくまで同レベルの場合ね。ミオとラビスの魔力レベルの差は、ラビスの方が1……もしくは2段階、上ってとこかしら? だから、今のミオがラビスを倒すのは、ちょっと難しいかもね……」と返答した。
「もう少し……歯ごたえがあると思っておったが、所詮はこの程度か!? くだらん、そろそろ決着(けり)を着けてやる。」
ラビスはそう言って左手で攻撃を防ぎながら、もう片方の右手で、紫色に輝く……光の球のような物を作り出した。その光の球は徐々に大きくなり、ついにはラビスの背丈程の大きさになる。
「くたばれ、神楽巫緒。ダーク・デストロイヤー……。」
重く、吐き捨てるように呟くと、ラビスはその紫色の光の球……ダーク・デストロイヤーを、ミオ目掛けて撃ち放った。
撃ち放たれたダーク・デストロイヤーは、ミオの放ったホーリー・ライトを打ち消しながら唸りを上げて突き進み、無防備となったミオに襲いかかる。
ズォォォォォォォォォンッ!!
雷鳴のような爆音、眩い閃光を放ちながら、土煙が巻き上がる。
しばらくして土煙が収まると、そこには激しいダメージを負って虫の息となったミオが、うつ伏せに倒れていた。
「ほぉ……、まだ息があるのか? たいしたものだ。だが、もう立ち上がる事もできまい?」
ラビスは倒れたミオに歩み寄り、仁王立ちで彼女を見下ろした。
「ハァ……ハァ…… どうしてもわからない。貴女は、なぜ……そこまで人間を目の敵にするの……?」
肩で息をしながら、それでも黙ってはいられないのだろう。ミオは苦しそうに、そう問い掛ける。
そんなミオに対し、ラビスは冷たく鋭い視線で見つめると、
「お前は地上界に巣食う……人間たちをどう思う? 下種な種族だと思わぬか?」と、逆に問い返した。
「下種……ですって?」
「そうだ。人間は動物や植物と違って、自分で考え判断し、行動できるという『自由』というものを創造主から与えられている。そしてその自由による行動が、人間という種族の基盤を築いている。
しかし、その実態はどうだ!?
他人のために、自然を守るために……。そんな心清らかな者は極僅かで、その逆に…他人を踏みつけ、虐げ、争い、傷を負わせ、命を奪う。挙句の果てに戦争を起こす。そんな輩ばかりだ。
そのような行為をお前はどう思う? そういった行為を人は『悪』と呼ぶのではないか?
しかも、清らかな心を持つ善行者よりも、他人を貶める悪行者の方が、栄光を手に入れる世の中。おかしな話だと思わぬか? これを下種と言わずして、なんと言うのだ?」
気持ちが昂っているのだろう。口調も昂ぶってくるラビス。
「ちなみに私事だが、ワラワの両親は小さいながらも一つの領地と、そこに住む村人を守り続けた領主であった。ワラワが言うのも何だが、お人好しで村人を心から愛し続けた、冴えない領主であったわ。だが、欲に塗れた余所者共が入り込み、村人たちに裏切られ、土地を奪われ……ついにはその命まで奪われた。」
「貴女の、お父さん……お母さんを……?」
「今の時代でもそうだ。栄光を手に入れた者。国を治めている者たちの心の中に、欺き、汚職、横領、恐喝、陰謀、隠ぺい……侵略、そういったものは一切無いと、お前は断言できるか?」
そう語るラビスは、まるで歪みの無い真っすぐな眼差しである。
そんなラビスに対し、
「貴女の言うことは、あながち間違いでは無いと思う。でも、誰もが進んで悪行を行っているわけではありません。そういったのは、本当に一部の人たちだけです!多くの人は、進んで悪行を行ったりしません!」
これだけは譲れないと言わんばかりに、激しい形相で言い返すミオ。
すると、ラビスはしばし間を置き……
「そうだ。確かにお前の言う通り、自身の意思で悪行を行うのは、僅かな数であろう。」と、意外な返事を返した。
しかし、ここまで言うと、再び鋭い眼差しでミオを睨みつけ
「だが、ワラワが人間共を下種と呼ぶのは、それだけの理由では無い! もっと質(たち)の悪い者たちが、世には蔓延っているからだ!」と声を張り上げた。
「それは自身で答えを出さず、周りに流され……同調する輩共!!」
「周りに流され、同調する……者?」
「お前の言う通り、自身で考え悪行を行うのは僅かな数だ。しかし、世の中には自分自身ではろくに考えもせず、世間の動きに同調する者たちがいる。たとえそれが、悪行であったとしても……だ。 そして、この手の輩が人間の大半を占めている。」
「そんなことはありません! 時には周りの流れに乗る人も大勢いるけど、それでも人は、良い事と悪い事の区別ができます! いくら流れでも、悪行の流れに乗る人なんているはずが……!?」
「ほぅ? では、お前は『魔女狩り』を知っておるか?」
ラビスはそんなミオに、憎しみとも悲しみとも見える、複雑な眼差しで見つめながら問いてきた。
「魔女狩り……? 実際に見たことはないけど、歴史の勉強や……雑学としてなら。」
「ある程度知っておるなら割愛するが、これに加担した多くの者たちは、真実を確かめもせず、いや……解っていても、それに目を瞑り、自分自身に火の粉が掛からぬように、周りの動きに同調していただけだ。」
「それは、そういう時代……、そういう国政でもあったから……!?」
「ならば、今の時代でお前たちに身近な話をしよう。この国にも、『いじめ』というものがあるだろう。アレはどうだ?」
「いじめ……?」
「発端は一人か二人かもしれん。だが、同じように真実や善悪から目を反らし、流れに乗って……もしくは、自身に火の粉に掛からんがために、同調して加担する者が多いのではないか? その結果、ときには死者が出ることになっても……。」
「…………」
「更に大規模なものが、『国叩き』だ。一つの国に色々な因縁をつけ、周りも一斉に叩きだす。 わかりやすい例で言えば、この国……日本叩きだ。有名なところでは、鯨問題であろう。 これも発端は一つの国だが、かなり同調した国もあるようだな?
だが、これはまだ平和な方だ。宗教などが絡むと、もっと根が深い。これも、戦争まで発展したこともあったはずだ。
更にもう一つ付け加えるならば、先ほどのワラワの両親を殺したのも、直接手を下したのは余所者ではない。そ奴等の根も葉もない話に惑わされ、それまでの恩を忘れて同調した、村民という愚民どもによるものだ。」
「…………」
「どれも発端は一部で、後はその他大勢が同調して、大事となっている。もし、一人一人の人間が、国が、真剣に考え……自身の答えを出していれば、こんな事にはならなかったかもしれぬ。 これを下種と言わずして、なんと言う?」
ここまで来るとミオは口論する気力まで失ったのか、地に伏したまま、黙ってラビスの話を聞いていた。
「だからワラワは考えた。多くの人間たちが、自分で考え答えを出せるという……与えられた自由を放棄し、周りに流され同調するだけであるのならば、一切の自由を奪ってやろうと!!
そう、まるで考える必要も無い……、物品や動物にでもしてやろうと!!」
「まさか……それが!?」
「そう。 人類形態変化計画だ。
ワラワの術やツーレムたちの力によって、ただ流され同調するだけの下種な者たちを、人間以外の物や動物に変化させる。
それが済んだ後に、自らの意思で悪行を行う者たちを抹殺し、始末する。そうすることによって、人間の世界は、他人を思いやり……自然を愛する、真に心の清らかな者だけとなる。理想の人間社会が出来上がるのだ!
これこそが、人類形態変化計画の全容だ!」
拳を握り締め、強い口調でそう叫ぶラビス。その姿には、まったく迷いといったものは見受けられない。
「他人を思いやり…自然を愛する、真に心の清らかな人間だけの世界……。理想の……人間社会?」
「どうだ? もう一度お前に問おう! ワラワと一緒に、理想の人間社会を作り上げていかぬか!?」
たしかに、欺きや争いの無い社会は、人間にとって本当に理想社会だ。ミオの心中に、ラビスの言葉が深く突き刺さる。
「でも……」
そう言い始めたミオは、自分の言葉に自信がないのか? まだ地に伏したままだ。しかし、拳だけは力強く握りしめられていた。
「うむ……?」
「たしかにそんな社会が築き上げられたら、本当に素晴らしいと思う。でも……、ボクが好きな人間たちの世界って、そういうのとは何か違うんです!」
「ほぅ……! 違う……とは?」
「ボクは天女族だけど、でも……人間社会の中で、人間の養父、養母に育ててもらいました。だから、ボク自身も人間と同じように、悩んで……迷い……、時には流され、そんなことも多々ありました。」
ここまで言うとミオは、まるで生まれたばかりの子鹿のように、ブルブルと手足を震えさせながら懸命に身体を支え、ゆっくり起き上がろうとし始めた。
「でも、その度にボクはいつも……自分自身を見つめ直してきた。そして、ときには反省し、ときには自分で自分自身を励まし。それを繰り返すことで、何が自分にとって正しいのか? 自分の中の正義とは……? それらを問いただせてきたのです。」
「それは、お前だから……そういう事ができたのであろう? 他の人間共は、そんなこと……」
「いいえ、他の人たちも一緒だと思います。貴女の言う通り、最初から最後まで心が清らかな人間なんて、極々……僅かでしょう。
それでも殆どの人は、正しいと思って進みながらも、ときには悪の道へ足を踏み入れたり、迷って流されてみたり……、元の道に戻ってきたり。行ったり来たりしながら、自分にとっての正しい道を探し続けていると思います。
でなければ……」
そう言いながら、震える足で懸命に大地に踏ん張り、しっかり胸を張り、凛とした眼差しでラビスを見据えた。
「でなければ……?」
ラビスは、そんな力強く起き上がったミオの姿に、一瞬戸惑いはしたが、フトっ……嬉しそうに口元を緩ませ、今まで以上に強い視線でミオに問い返す。
「人間の歴史が、700万年も続くはずがありません! 貴女が手を下すまでも無く、もっと……もっと早く、滅んでいるはずです!!」
自分の考えや言葉が正しいなんて、今ここでもハッキリと断言は出来ない!
それでも、自分が正しいと思うものを信じて生きてきた! そう、教えられてきた!
これだけは、ハッキリと言いきれる!!
――そうだよ……ミオ。本当に正しいかどうかなんて、そんなの関係ないの。アンタはいつも、迷いながらも自分が正しいと信じる道を、一生懸命突き進んできた。そんなアンタだから、アタシは誰よりもアンタが好きなんだよ!―
これまで黙って戦況を見つめてきたシグーネ。
いつもは冷酷で、稀に悪戯っ子のような眼差しであるが、今ばかりは……まるで母親か、姉のように優しい眼差しで、ミオの力強い姿を見つめていた。
「なるほどな! つまり、お前は『人間は、今のままで良い……』、そう言うのだな?」
「いいか……どうかは、わかりません! でも、貴女やボク個人らが、その存在をどうこうしていいとは言えません。
人間の在り方は、人間自身が決めるべきです!
ラビスさん、貴女は誰よりも人間世界の行く末を案じています。人間の存在を無くすことよりも、人間が正しい生き方をできるように、それこそ……一緒に考えていきませんか!?」
「人間の下種さは、変わりはせん! お前の言葉を返すなら、700万年……下種のままだ!もはや、誰かが手を下さねばならぬのだ!!」
「だったら、ボクは何があっても、人間を守り通します!!」
自身が言うとおり、いいか……どうかではなく、今…自分が信じることを貫き通す。
迷いがとれたミオは、再び臨戦体勢を取るように身構えた。
完全に打ち倒したと思っていたミオが、再び戦う姿勢を見せた事に、ラビスはフッと鼻で笑うと、
「そこまで言うのであれば、ワラワも声を掛けるのはここまでとする。そう、お前はワラワの敵だ。今この場で、この付近の人間共と一緒に消し去ってくれるわ!!」
そう叫ぶと、万歳するように高々と両手を上げた。
すると、その両手の遥か上空に、紫とも赤とも青とも言えない……何とも怪しげな色の光を放つ球体が、火花を散らすように輝きだす。
更にそれは、ラビスの腕に力が篭もるたびに、徐々に徐々に大きくなっていき、やがて辺り一面を、街を……、暗い影で覆い尽くす程の、大きな大きな球体となった。
「これが、ワラワの最大級の魔力を使った……、ダーク・デストロイヤーだ。」
「あ、あ……あまりにも大きすぎる。こんな大きな闇のエネルギー、見たことないですぅ!?」
そのあまりの巨大さに、傍で眺めていたセイナは、呆然と立ち尽くす。
「これだけの魔力なら、この辺一帯どころか……神田川県全域の人間が、一気に消滅するだろうね」
さすがのシグーネも、表情が少し強張っている。
「ラビスさんっ!! もう……止めて下さい! でないと、ボクは本気で……!」
右手で魔法を放つ構えをとりながら、必死に引き止めようとするミオ。
「本気でなんだ!? つい先程まで寝そべっていたお前が、ワラワに一矢を報いることができると言うのか?」
ラビスは、もう一度受け止めてやると言わんばかりに左手を差し向けると、冷ややかな笑顔で、そう言い返した。
「く、くそぉ……。ホーリー・ライトォォォっ!!」
ミオの右掌から眩い光が広がると、再び真っ白な光の束が、ラビス目掛けて放たれた!
グォォォォン!!
またもホーリー・ライトを、左手の魔力の壁で受け止めるラビス。
「無駄だ。こんな物……ワラワには通じないことは、先程身に染みたはず。」
紫色に発光するラビスの左手。その手は完全にミオの光魔法を食い止め、1㎜程も侵攻を許す気配が無い。
その様子を見守りながら、
――ミオ……、アンタの真の力を引き出しなさい。そうしなければ、ラビスは……いえ、ラビスの中に潜む、真の脅威は倒せないわ。そう…アンタが言う通り、『この地上界』は、アンタが守らなければならないのよ!― シグーネは、そう呟いていた。
そんな中、ミオの光魔法を、左手一本で少しずつ押し返し始めるラビス。
「やはり、その程度か……? まったくもって話しにならぬ。ならば、そろそろこのダーク・デストロイヤーを、この地に放たせてもらうとするぞ!」
ラビスはそう嘲笑うと、もう片方の右腕で支えていた巨大な球体を、ゆっくりと都心部の方へと向け始めた。
「や……やらせない~っ! おぉぉぉぉぉぉぉぉっ!!!!!」
まるで地響きでも起こっているのではないかと錯覚するほどの、激しいミオの叫び!
その叫びに同調するかのように、ミオの全身が眩い光で覆いつくされていく。
そして、魔法を放っていた開いた掌を少しずつ握りしめ、人差し指一本だけをラビスへ向けた!
そう、それによって今まで広範囲に放たれていた光の束が、指先程細く……しかし更に光を増し、集約された『一筋の閃光』と化したのだ!
「くらえぇぇぇっ! ホーリー・レイ!!」
指先程の眩い光の直線が、再びラビスを襲う。
「お前の魔力レベルでは、ワラワに勝てぬわ!!」
そう、余裕で受け止めるラビス。
だが、今度は先程までとは勝手が違った。魔力を指先に集約したこともあって、力の密度が違っているのだ!
一本の閃光は、受け止めるラビスの左手に風穴を開けるが如く、キリキリと食い込んでいく。
「ま……まさか!? ワラワが押されるのか!?」
そう呟いた瞬間、ラビスの身体が眩い白い光に覆いつくされた。
そう。威力に押された左手を弾いて、白い閃光は、ついにラビスの左胸を貫いたのだ!!

「うぉぉぉぉぉぉっ!!?」
衝撃で、勢いよく弾き飛ばされるラビス。
同時に空中に漂っていた巨大な球体は、まるで花火のように四散し、消滅していった。
「やったぁぁぁ!! ミオちゃん!」
「ラ……ラビス様……!?」
躍りまわるセイナに、茫然と立ち尽くすプウーペ。ミオは、そんな対照的な二人の姿を見て、自分の魔法が打ち勝ったことを、やっと悟ることができた。
「大したものだ。さすがはウィンディーの娘……」
弱弱しい声が、ミオの耳に入る。
見ると、そこには必死で起き上がろうとする、傷ついたラビスの姿。更にその全身は、白い光の粒子が満遍なく包み込んでいる。
「ラビス様、まさか……それはァ!?」
プウーペの目に忘れようとも忘れられない、二百三十年前の恐怖が蘇る。それは、ラビスがウィンディーに敗れたときと同じ光景。
闇属性を操る者が光属性に敗れたとき、全身が光の粒子に覆われ、やがて石箱と化し、身も魂も封印されてしまう。
「か、神楽ミオ……! お願いデス! ラビス様の……ラビス様の光の術を解いてくだサイ!」
元々…一体の人形であったプウーペは、感情表現というものがあまり得意ではない。にも拘わらず、この時ばかりは目に大粒の涙を溜め、ミオにしがみ付いて懇願してきた。
「う、うん……今すぐ……」
ミオは両手を広げ、ラビスを包み込んでいる光の粒子を自身の身に、取り込もうとする。だが、そのとき……。
「神楽ミオ、その必要はない……」
光に包まれ、徐々にその姿が消えかかっているラビスが、そう答えたのだ。
「ラビス様、そんなわけには……!」
「これで良いのだ、プウーペ。お前には黙っておったが、ワラワの中には表に出してはならぬ、もう一人の脅威が住みついておる。このまま一緒に封じ込めてしまう方が最善なのだ。」
「何を仰っているのカ、意味がわかりまセン! それに……帰ってカラオケを熱唱するのでショウ? どうせ私をマイクか…何かに変化させて、遊ぶつもりだったのでショウ? だったら、元に戻って……」
「マイクに変化か……? それはそれで、面白そうだな。考えてもおらんかったぞ! でも、もう……良い!」
ラビスはそう言って、優しく微笑んだ。
「ラビスさん。貴女……もしかしてワザと挑発して、ボクを奮起させた……!?」
その問いに、ラビスは何も言わず微笑みで返す。
「血は通っていなくとも、ウィンディーはワラワにとって実の妹のような存在であった。その娘であるお前は、姪のような存在でもあるわけだな。」
それはまるで、娘に対する母親のような優しい笑顔。
「良いか……? 光の天女、神楽ミオ。
この時代……この地上。お前の光の力で照らし続けるのだ……。決して闇に……。いや、たとえ……相手が神と名乗っても、負けぬようにな!」
ここまで言うとラビスは、光の粒子に飲み込まれるように姿を消していった。
そして、それと引き換えのように、その場所には小さな石の箱が、ポツンと残っていた。