2016.04.23 Sat
妖魔狩人 若三毛凛 if 第20話「 BadEnd~妖魔狩人編~」
□前回のあらすじ□
妖木妃との直接決戦において、たった一つの凛の判断ミス。
これにより、凛はもとより他の三人の妖魔狩人も、為す術もなく倒されてしまった。
「そこのお前。すぐに白陰のところへ行き、大至急、料理のできる妖怪にここへ来るように伝えよ」
妖木妃に、そう命じられた花の妖怪……女夷。元々たいした戦闘力もなく、争いごとを好まない妖怪ではあるが、同じ植物系妖怪の誼み(よしみ)である妖木妃に逆らえず、こうして日本までやってきてしまった次第である。もっとも妖木妃にとっての女夷は、ただの雑魚部下その一であり、顔と名前の一致すらしていないだろうが。
命じられたまま白陰の元へ行くと、指示に納得した白陰は調理のできる妖怪たちを選りすぐる。なんといっても妖木妃が直々に食する料理だ。不備があってはならない。
料理の知識、腕前、様々なテストを重ね、ついに彼は四人の候補者を選出した。
「で、これがお前が選んだ調理のできる妖怪たちか?」妖木妃は、眼前に並ぶ四人の妖怪たちを見渡し、その脇にいる白陰にそう尋ねた。それに対し、「はい」と頷く白陰。
「よかろう、着いて参れ。お前たちが腕を振るう材料は、すぐそこにある」
妖木妃はそう言うと、自ら先頭に立ち、白陰と四人の調理師妖怪を引き連れ、拝殿の扉を開けた。
拝殿の中で横たわる四つの人影。それは、凛、優里、千佳、瀬織の姿であった。
「そやつらは気を失っているだけで、まだ死んではおらぬ新鮮な材料じゃ。そこで、お前らの役目じゃが、各々一体ずつ持ち帰り、それぞれ得意とする調理を施し、誰の料理が一番美味いか!?料理対決をしてもらうことにする」
「おおお……」
「ただし、一つだけ条件がある。素材は全てペチャンコ、つまり押し潰してから調理すること。ワシもこう見えていい歳だ。一度押し潰して柔らかくなった料理が、今では好みじゃ。その後は、和洋中一切問わぬ。期限は三日後の正午。いいな!? 自慢の腕を奮った見事な料理をこさえてみよ」
妖木妃の言葉を聞き、四人の妖怪は凛たちのもとに集まり、それぞれ品定めを始めた。直接肌に触れ、匂いを嗅ぎ、後が残らぬように軽く舌で触れ、味覚を確かめる者もいた。
すると、一人の白く小柄な妖怪が納得したように立ち上がると、凛を指差し妖木妃と白陰の了承を求めた。無言で頷く両者。それを確かめると、そいつは凛の身体を抱え上げ、静かにその場を立ち去っていった。
残る三人の妖怪は、優里の身体をジッと見つめている。どうやら三人とも、自分の料理の材料には優里が相応しいと決めたようだ。
特に二人の妖怪。一人は真夏だというのに黒いコートを羽織い、コート以外も全身黒尽くめの出で立ちに、背中に二本の巨大包丁をX字に背負っている。もう一人は子どもと変わらぬほどの小柄で、まるでマカロンのような頭部で、しかも二頭身の身体つき。この二人は互いに睨み合ったまま、一歩も引きそうにない気配を見せていた。
そんな二人を「やれやれ……」といった雰囲気で見つめていた、無表情な白い面を被った残る一人の妖怪。彼は何も言わず二~三歩進みと、なんと、千佳の身体を指差した。「赤い妖魔狩人でいいのか?」白陰の問いに白い面の妖怪はコクリと頷き、そのまま千佳の身体を担ぎ上げ無言で去っていった。
あとは、黒尽くめと二頭身の二人の妖怪。どちらも高い戦闘力の持ち主のようで、睨み合うだけで、地鳴りが起きそうな気配がしている。そんな二人を見兼ねたように妖木妃が声を掛けた。
「欲しいものは力尽くで奪え。いつものワシならそう言うであろうが、今はあえてこう言おう。時間が惜しい、争わずに決めるがよい」
その言葉に二人は渋々頷くが、とは言ってもどのようにして決めろと?と言いたげな表情である。そこに白陰が間に入った。「仕方ない、ここは日本。日本流の平和な決着法……『ジャンケン』で決めるとしよう」
「ジャンケン……ポン!」白陰の掛け声で二人とも握りこぶしを出す。「アイコで……ショッ!」「アイコで……ショ!」と二~三回アイコが続き、最後に二本指と握りこぶし。
小さなガッツポーズを決めたのは、小柄な二頭身妖怪。彼は嬉しそうに優里の脇に立つと、驚いたことに身体の半分を占める頭が、更に膨らむように大きくなっていった。そしてガマ口のような大きな口を広げ、パクリと優里の身体を咥え込んだ。本当はそのまま丸呑みしたいのだが、そこは我慢。優里を咥えたまま、その場を立ち去っていった。
最後に残された黒尽くめの妖怪。仕方ない……といった表情で、瀬織を担ぎ上げると、そのまま霧のように去っていった。
そして三日後の正午。拝殿脇に並べられた長テーブル。白いクロスで覆われており、上座に腰掛けているのは、当然……妖木妃。妖木妃から向かって右側には、白陰。左側にはムッシュが腰掛けている。
司会進行役は、なぜか花の妖怪である女夷。マイクを持つその手は、ガタガタと震えている。
「わ・わ・わ・私の……記憶が確かならば……、こ・こ・今回……揃えられた材料、そ…そして……それを料理した対決というのは、し・し・神話……の世界、まだ……多くの神族が……、地上を支配していた……ときまで、遡らなければ……いけないはずです……」
震えたマイクに震えた声。そして、震える手で読み上げる数枚のメモ紙。
「何を言っておるのじゃ? あの娘は……?」
「ムッシュであろう? あんな物を読ませたのは!?」と白陰がムッシュに睨みを利かす。
「うむ、やはり料理対決となれば、こうでなくてはならんと思いましてな!」当のムッシュは悪びれもせず、自慢のカイゼル髭をピンと伸ばし、楽しそうにニカッ!と笑った。
そんな楽しそうなムッシュとは裏腹に、今にも卒倒しそうなくらいオロオロしっぱなしの女夷。震えながら更に進行していく。
「い・い・い・今こそ……よ・よ・よ・甦れ・れ・れ……、伝説の……て・て・鉄人……、も…もとい、鉄の妖怪……。ア・ア・ア・アイアン……イ~~~ビル~~~ッ!!」
それが合図となったのか、拝殿前の参道を大量の白煙(ドライアイス?)が、覆い尽くす。そして、その白煙の中から四人の影が姿を現した。

「こんな臭い演出、やる必要があるのか?」さすがの妖木妃も苦笑い。
「ま……まずは、一人目。世界を股にかけて食べ歩く、流れの料理人……! 某特務機関超能力支援研究局(通称バ◯ル)所属のレベル7テレポーターから、『りゅりょりゅにゅ‥‥ごめん、噛んでしもた!』とまで言わさせた、変態妖怪……るりょけん!!」
最初の紹介で登場したのは、真っ先に凛を担いで去っていった妖怪。真っ白な毛に覆われた、丸々とした流線形。つまりアザラシの姿をした、強いのか?弱いのか?まるで見当のつかない。こいつは妖木妃に手を振りながら、調理台の前についた。
「あんなの、ワシの部下におったか?」怪訝そうな眼で眺める妖木妃。
「つ…つ……続きまして、調理の腕も然ることながら、ダンジョン探索が三度の飯より大好き! 別名黒き料理師、ビーター妖怪……霧斗!!」
現れたのは、あのコートを含めた頭の先から足の先まで全身黒尽くめの妖怪。その素顔はまだ十代少年の面影を残し、今風のイケメン顔であった。霧斗は礼儀正しく妖木妃に一礼すると、次の調理台の前についた。
「ビーター妖怪? 噂では聞いたことがある。なんでも神獣と互角に戦えるとか。そうか、コヤツのことであったか!」妖木妃はそう言って、ニヤリと微笑む。
「つ・つ・次は……、絵の前にいるのは、すべてオレの餌!人も獣も、その気になれば鯨でさえ一呑み! ま・ま・丸呑み妖怪……呑雌鬼(どんしおに)!!」
この紹介で現れたのは、マカロンのような頭の小柄な二頭身妖怪。呑雌鬼は妖木妃の前を通る際、大きな口で歯を剥きだしたままニカッ!と笑って、調理台についた。
「あーっ、知っているぞ……コイツ! たしかに以前インドで、象を一頭丸呑みしていたのを、見たことがある!!」白陰が思い出したように、指を指した。
「さ・最後は……、料理も獣化も状態変化も、そして固めでも全てお手の物!いつの間にか一味に加わっている謎の仮面妖怪……ミスターW⊥(ヴァイテ)!!」
シルクハットに黒いマント。千佳を連れ去った時以上にお洒落な出で立ちで現れたのは、真っ白の無表情な面を付けた男。妖木妃に軽く会釈すると、静かに調理台についた。
「ほぉ!なんとなくですが、コヤツからはアジアではなく、我輩の好きな欧州の匂いがしますな!」ムッシュの嬉しそうな声。
「ほ・ほ・本日……、以上四名が……腕を振るった料理を、ひ・ひ・披露……致します!! し・し・し・審査員の皆様方、公平な審査、よろしくお願いいたします……!!」
女夷の言葉に再び四人が、妖木妃たちに向かって会釈した。
「し…進行は引き続き……私、女夷がさせていただきます……。な・なお……、調理された妖怪の方々の中には、人前でお話をされるのを苦手としていらっしゃる方もおられるようなので、料理の説明なども全て、私がさせていただきます……。では、最初は……るりょけん氏から……」
女夷はそう言うと参道に向かって振り返り、そこで待機している数名の妖怪たちに合図を送った。
すると、二~三人の妖怪たちが、手押しワゴンを運んでくる。ワゴンの上には、人ひとり横たわれそうな大きさの銀の角皿が乗っていた。ワゴンは妖怪るりょけんの調理台の前に止まると、角皿が調理台へ移された。皿には蓋が掛けてあるので、まだ中身はわからない。
妖怪たちの手によって、蓋が取り払われる。
「おおっ!?」妖木妃、白陰、ムッシュ、そして周りで見ている大勢の妖怪たちの、驚きの声があがった。
角皿に寝かせるように乗せられているもの。それは、横に厚さ5ミリメートル程まで薄く押し潰された、若三毛凛の姿であった。
「ほぅ、一番目から黒い妖魔狩人の料理か!?」少し意外だったような口調の妖木妃。
「見たところ、たしかにペチャンコにはなっているが、それ以外……何も調理されていない、まるっきり生(なま)のように見受けられるが……?」
白陰の言うとおり、角皿に乗っている凛は戦闘服を着たまま綺麗に押し潰されているが、それ以外は生きていても不思議ではないほど無傷な状態であり、どう見ても手を加えられた様には見えない。
「いや、アレは結構……良い仕事をしているようですぞ!」だが、ムッシュだけは何かを見抜いたようにそう呟いた。それを耳にした妖怪るりょけん。わかってくれたか!と言わんばかりに、ニヤリと微笑んだ。
るりょけんは刺身包丁を手に取ると、凛の左足の脛の部分を、一口大の大きさに三~四つほど切り分けた。そしてソレを一枚ずつ小皿に乗せると、助手の妖怪に長テーブルまで運ぶように指示を出した。
命じられたまま、小皿を妖木妃、白陰、ムッシュの前に置く。
「まずは、一口……味見をしてみろ、ということですかな?」ムッシュはそう言うと、箸で切り身を摘むと、そのまま口まで運んだ。妖木妃、白陰も後に続く。
モグ……モグ……モグ……
「ほぅ!」「おおっ!」「うむ、悪くない!」それぞれから笑みが溢れる。
「え・・え……っと、説明させて頂きますと、それは『黒い妖魔狩人の一夜干し』だそうです……」女夷がるりょけんの言葉を、改めてマイクを通して語りだした。
「まずは、黒い妖魔狩人を重さ五百キログラムの鉄の重石で押し潰します。程よく均等に押し潰されたのを確認したら、今度は黄金のロールプレス機で圧延いたします」
「ロールプレス機……?あの、回転するローラーを使った機械か? わざわざそんなもので……?」
「ロールプレス機を使った理由は、より薄く……そして、より均等にしたかったこともありますが、一番重要なのは、コレを手に入れるため!……だそうです」女夷がそう説明すると、るりょけんは容量1リットル程のガラス製の瓶を、高々と上げた。瓶の中には、半透明の黄色染みたトロリとした液体が入っている。
「瓶の中身は、黒い妖魔狩人の汗や分泌液、そして尿などが程良く混ざり合った純粋な体液です。ロールプレス機の利点は、このように身体の隅々から体液を絞り取ることができるのです!」
「なるほど、一昔前の洗濯機に付いていたローラーと同じですな!」
「ペラペラになった身体を風通しのよい日陰で干しながら、その体液を何度も塗り続け、味を染み込ませるそうです!」
「なるほど!本来ならば、土臭くて味気ない十代前半のガキなのに、それによって適度な塩分や酸味によってほのかな甘味が引き出され、この美味さになっているのか!?」
さすがの妖木妃も口元が緩まずにはいられない。
「えっと……、それで驚いてもらっては困る。本番はこれからだと、るりょけん氏は申しております!!」
「なんだと、この料理で終わりじゃないのか!?」
女夷の言葉に、誰もが再び調理台に注目した。皆の注目の中、妖怪るりょけんは助手の妖怪に指示を送る。しばらくすると二~三人の妖怪たちが、高さ50センチメートル直径1.5メートル程の円筒のような物を運んできた。
「七輪か!?」白陰の言葉の通り、それは通常より大きめの七輪。中には赤々と燻っている炭が積み込まれてあり、充分熱せられた、金網が乗せてある。
るりょけんは炭火の状態を確認すると、ペラペラと風になびく凛の身体を、金網の上に静かに乗せた。
パチッ…パチッ…と炭が弾ける音と共に、香ばしい匂いが漂いだした。ピラピラに伸びきった凛の身体が、熱を帯びてくるとジリジリと僅かながら縮みだす。そして、頃合いを見て裏表ひっくり返す。今まで火に炙られていた面が、少しだけ狐色に焼き目が付いていた。

更にいい匂いが漂い出した頃、るりょけんは凛の身体を引き上げ、調理台の皿の上に乗せ直した。
「えっと……、ここで大事なのは、決して焼き過ぎないことだそうです。全体を軽く炙るだけで、適度に温まる程度に火が通るのが、一番良いとのことです」
女夷の解説に、妖怪るりょけんは大きく頷いた。そして、先程と同じように一口大の大きさに切り分けていく。
妖木妃たちの元へ運ばれた切り身の他に、今度は小皿に入った濃い橙色の液体が、一緒に配られた。
「炙った切り身を、その皿のタレに付けて食べて欲しいそうです!」
言われた通りに切り身にタレをつけ、口へ運ぶ。
「おおっ!なんとっ!!?」「こ…これは凄いっ!」「うむ、悪くないどころか、これは絶品ですな!!」先程以上の歓喜の声を上げ、目を丸くし、嬉々とした表情の妖木妃たち。
「温めたことで切り身の甘みが遥かに増し、更に焼き目の香ばしさが食欲を倍増させる。そして……問題は、このタレだっ!?」
誰もが同様に口走る問いに、るりょけんはボソボゾと女夷に返答を命じる。
「そのタレは先程の体液をベースにし、酒とみりんで味を整え、紅葉おろしを加えたものだそうです!」
「なるほど! 同じ黒い妖魔狩人の体液ですか!?だから違和感無く切り身と調和するのですな。そして紅葉おろしの辛味が、さらに切り身の甘みを引き出す!! 見事な仕事ですぞ!」
さすがのムッシュも、まるで感服したかのように満面の笑みを浮かべ、自身の髭を弄くっている。
「素晴らしい。できることなら、この干物の太腿の部分を味わってみたいが……」
妖木妃がそう呟くのを見計らったように、もう一品の皿が前に差し出された。「もしや?」妖木妃は調理台にいる妖怪るりょけんをみると、彼は腿の部分を切り取った干物をチラリと見せた。
「一番軟らかく、一番素材の味が確かな、内腿の部分だそうです」助手妖怪が、さり気なく付け加えた。
出された内腿の切り身にタレをつけ、口へ運ぶ。
「ぉぉぉぉぉぉぉ………」妖木妃は、もはや言葉を忘れそうになった。爽やかな甘みと塩っぱさと、癖のある酸味が奏でる見事なハーモニー。それは至高と呼ぶに相応しい、旨味の世界であった。
「で…では、次の方に進みます! 次は人間退治だけでなく、神獣まで成敗する最強の妖怪剣士、霧斗氏です!」
女夷の掛け声が終わると、またも手押しワゴンが運ばれ、霧斗の調理台の前に止まった。ワゴンの上にはトラックのタイヤを重ねたような、大きな蒸籠が乗っている。
「今度は、蒸し料理か?」思わず問いかける白陰に「いや、蒸気が吹き出していないところを見ると、蒸籠はただの演出上の飾りでしょうな!」とムッシュが答えた。
数人が蒸籠を調理台の上に乗せると、ニヤリと微笑む霧斗が、勢いよく蓋を取り外した。
眼に飛び込んで来たのは、鮮やかなピンク……いや、桜色と、清々しい緑色! それは桜色の丸まった物体を、大きな緑色の葉で包んだものであった。
「柏……もち……?」そう呟く白陰。「いや、あの葉は柏では無い。アレは桜の葉……」自身が植物系妖怪であるため、植物に詳しい妖木妃がそう返した。
「そ……そ、そうです! 霧斗氏の作られた料理は、妖怪桜の葉で包んだ、『青い妖魔狩人(棚機瀬織)の桜餅』です!!」
「おおおっ!!」女夷の説明に、多くの妖怪たちから歓声が上がる。
たしかに言われてみると、大きな桜の葉のすぐ下には、厚さ1~2センチ程の平たい餅のような物が二つ折りにされ、その間には見るからに甘そうなこし餡が収まっている。
「では、あの桜色の平たい餅が、青い妖魔狩人なのか!?」「そのようですな、良くご覧になるといい。餅の端にグルグルと眼を回した青い妖魔狩人の顔が見える」
そのような会話が進む中、霧斗は背中に背負った大きな包丁を一本抜き取ると、鮮やかな太刀筋で、桜餅を数十等分に切り分けた。そのうちの三切れを皿に取り分けると、助手妖怪に妖木妃たちのテーブルに運ばせた。
テーブルに並ばれた桜餅の切り身。ほのかな桜色と微かな桜の葉の香りが、食欲を誘う。
「ほぅ。たしかによく見ると、餅のように見えるが、間違いなくペチャンコになった小娘じゃ。しかも生ではなく、焼き目が入っておるな!」
妖木妃はそう呟くと、黒文字(和菓子用の楊枝)で更に小さく切り分け、口へ運んだ。
口へ入れた途端、桜の花の甘い香りが口内に広がる。柔らかくなった餅を歯茎や舌で噛み潰していくと、コクのある甘さのこし餡が溶けるように流れ出る。
「うむ、これは見事じゃ!」思わず妖木妃が唸った。
「さ……さて、ここでこの桜餅の調理方法を説明いたします!!」女夷が自身に注目を向けるように金切り声を上げた。
「さ・最初にお話したとおり、この料理のメイン食材は、青い妖魔狩人です! まず捉えた青い妖魔狩人に、十年ほど寝かせた『さくらんぼ酒』を飲ませます。未成年でアルコールに弱い青い妖魔狩人はすぐに酔いが回り、眼を回してひっくり返りました。」
「なるほど。頬も含め、全身が桜色なのは酔っ払ったせいか!」
「更に、グデグデになった青い妖魔狩人を、これまた桜の木で作った大きな枠の中に寝かしつけ、全身が浸るまで『さくらんぼ酒』を注ぎ込みます。そして、その身体におよそ200キログラム程の重しを乗せ、ゆっくりとジワジワ押し潰していき、そのまま丸一日置いておきます。そうすることによって、さくらんぼ酒がじっくりと、身体に染みこまれていくわけです」
「元々青い妖魔狩人は色白だったから、だからここまで綺麗な桜色に仕上がったわけだ!!」
「後は、ペチャンコになった身体を吊るし干しにして、余分なアルコールを抜いていきます。そして再び麺棒で厚さ1~2センチほどまで押し伸ばしたあと、鉄板の上で軽く両面を焼き上げ、焼き目と香ばしい香りを付けます」
「見た目は若いが、見事に和菓子の調理法を身につけているな!」
「最後に身体の中心にこし餡を乗せ二つ折りにし、そのまま妖怪桜の葉で包んで完成です!!」

女夷が説明を終えると、盛大な拍手が霧斗へ送られた。大げさに騒ぐわけでなく、回りに軽く会釈をし、拍手に答える霧斗。
「だが、それだけではあるまい!?」そんな歓声を遮るように、妖木妃が一喝した。
「この美味さ、それだけではあるまい。おそらくその秘密は……餡! そう、餡にあると思えるのだが!?」
そんな妖木妃を後押しするように、ムッシュが更に付け加えてきた。「妖木妃殿の仰るとおり、問題は餡ですな! 通常、和菓子の餡は、甘味を引き立てるために、隠し味に『塩』を一摘み入れると聞きます。ですが、この餡は甘味だけでなく……深い独特なコクのようなものも感じ取れる。おそらく隠し味に使ったのは、塩では無いのではないかと……?」
妖木妃とムッシュの問いに、霧斗は不敵な笑みを浮かべた。それは剣士が最高の好敵手に出逢えたような、そんな含みを込めた笑みだ。
「さすがは、おふた方……。と霧斗氏は申しております」女夷がそう述べると、更に霧斗が女夷に耳打ちをする。
「たしかに隠し味に塩は使用せず、ある特別な物を使ったそうです。その、ある特別な物とは……『青い妖魔狩人が身に着けていた下着』!!」
「し……下着……だと?」白陰が驚きの声を漏らす。
『身に着けていたパンツやブラなどの下着を寸胴鍋に入れ、たっぷりの水を注ぎます。それを火に掛け、八割以上の水が蒸発するまで存分に煮込みます。すると僅かに残った湯は、下着のエキスと旨味が凝縮された、味の濃いダシ汁になっているというわけです!」
「おおおっ!!?」
「そのダシ汁を十分に冷ましたあと餡に注ぎ込み、しっかりと練り上げるんだそうです!」
「なるほど! 下着に染み込んだ『汗』が塩分の役目になり、同様に染み込んでいる他の匂いや分泌物が、あの独特のコクになったというわけですな!」
そう言いながら、感心のあまり何度も納得したように頷くムッシュ。
「うむ、文句ない! 見事じゃ……霧斗よ!」妖木妃も讃美の言葉を述べた。
「では、では……、次の方に参ります。次は人間を丸呑みすること数百年!丸呑み世界一を誇る、妖怪……呑雌鬼氏です!」
紹介の後は、今まで通りワゴンが運ばれる。ワゴンの上には大きな丸皿が乗っており、中身を隠すように、半径50センチ程のドームカバーで蓋をしてある。今度は調理台に移す前に、呑雌鬼がドームカバーを外し、中身を披露した。
そこには、縦20センチ・横40センチ・厚さ5センチほどの、まるでコピー用紙を数百枚ほど重ねたような、そんな白っぽい塊が置いてあった。
「なんだ……あれは!?」
周りがどよめく中、呑雌鬼の大きな口が、勝ち誇ったようにニヤリと笑う。そして、コピー用紙の一番上の紙をめくり上げるかのように、その白い塊の一番上の辺りを、ペラリとめくり上げた!
な・な・な……なんと! めくり上げられた紙のような薄い物には、半開きの口に、グルグルと眼を回し、呆けた『優里』の顔があった!!
「な、なんだと……? もしかして、あの白い塊は白い妖魔狩人を折り畳んだ物なのか……!? だ・だが……あの薄さはなんだ!? どう見ても……紙よりも薄いぞ!?」あまりの驚きに、思わず立ち上がってしまった白陰!
いや、白陰だけではない。周りにいる妖怪たち全てが、驚きを隠せなかった。
「え……えっと、皆さんが思っておられる通り、ここにあるのは、極限まで薄く伸ばしてから折り畳んだ、白い妖魔狩人だそうです!」
女夷の解説が始まると、誰もが息を飲んだように静まりかえる。
「まず、捉えた白い妖魔狩人をうつ伏せに固定し、上部から『ランマ』を使って、押し潰すところから始めます」
「ランマって……!?」「ほ・ほれ……、道路工事なんかで、ダダダダダッ!!ってホッピングみたいに上下振動し、アスファルトを押し固める機械だよ!」「あ…あんなんでか!?」
「あくまでも適度に押し潰すのが目的なので、別にランマじゃなくてもいいそうですが、激しい振動で、正気を失ったようにヘロヘロに悶えていく妖魔狩人の姿が面白いので、あえてソレを使ったそうです!」と、周りの声に答えるように、女夷が説明に補填をした。
「厚さ数センチメートルまで押し潰したら、それを大きな金パットに入れ、切り刻んだパイナップルと一緒に一晩漬け込みます。そうすることで、肉が更に柔らかくなるそうです!
翌日、のし台の上に妖魔狩人を平らに敷き、彼女の足元から麺棒を手前に巻きつけ、体重を乗せて転がしていきます。一通り転がしたあと麺棒から引き離し、再び足元から巻きつけ、また同じように押し転がしていきます」
「ふむふむ、うどんを打つのと同じ要領か!」
「ポイントは、生地同士が引っ付き合わないようにすることと、押し潰すことで中のエキスが外へ逃げないようにするために、特殊な和紙を間に挟んでおくことです。そうして、この作業を四~五十回ほど繰り返します!!」
「し……四~五十回だと!?」
「丁寧に時間を掛けて作業することで、このように裏面が透けて見えそうなくらい、すなわち……厚さ1/100ミリメートルまで薄く押し延ばすことができるのです!!」
「た……、たしかに、職人技だ……!?」改めてその薄さを見て、誰もが驚愕を隠せない。
「そして、薄く延びた生地を20センチごとに折り畳んでいきます。こうして仕込んだのが、今……目の前にあるコレ、白い妖魔狩人の『ミルフィーユ・カツ』です!」
「み…ミルフィーユ・カツ!?」
「今からコレにパン粉をまぶし、油で揚げて、仕上げに入ります」
女夷の説明が終わると同時に、優里の身体は調理台の上へ運ばれた。台の上には金パットが置かれており、中にはたっぷりのパン粉が敷き詰められている。溶き卵とパン粉、交互に塗り固められていく優里。
その傍らで、他の助手妖怪たちが大きなコンロを用意し、大鍋で大量の油を沸かしている。
カツ(優里)の準備を終えると、呑雌鬼は自らの指を油に突っ込み、油温を確認する。「うむ!」そう頷くと、助手妖怪たちにカツを鍋に投じるように命じた。
ジュワァァァァァッ!! 油が弾けると同時に、香ばしい匂いが辺りに漂いだす。底に沈んでいたカツも、ゆっくりと浮き上がってきた。呑雌鬼は、それを菜箸で突きながら、時折ひっくり返し、満遍なく火を通していく。
十数分経ち、油の弾け具合から頃合いを見定めると、呑雌鬼は大きなザーレン(油こし)で、カツを掬い上げた。そして調理台の上のまな板の上に乗せる。
濛々と上がる湯気と、香ばしい匂いを放つ大きなカツ。呑雌鬼は大きな包丁を両手で握り、ザクッ!ザクッ!と均等に切り分けていく。
そして、ついに妖木妃たちのテーブルに、切り分けられたカツが並べられた。溢れ出る肉汁と脂の甘い匂い。それだけで、ご飯三杯はいけそうなくらい、いい匂いだ。
「まずはソースも何も付けず、そのままガブリと齧り付いてください!」女夷の言葉に、カツを摘み、そのまま口へと運ぶ。
ガブッ! 一噛み。たった一噛みで、口の中に大量の肉汁が崩壊したダムのように溢れだした。一気に肉の甘味が口の中に広がっていく。
「おおおっ!なんという……美味さだ!!」思わず歓喜の声を上げる白陰。
「いや、たしかに美味いが、驚くべきことはそれだけではありませんぞ!」と言葉をつけ加えるムッシュ。
「うむ、驚きべきことは、この肉の柔らかさだ!口内にちょっと圧力をかけるだけで、切れ目から解れるかのように、簡単に食いちぎれる!!」あの妖木妃ですら、喜びのあまり、冷静さを欠いている。
「美味しさの秘訣は、ミルフィーユ・カツとして仕上げたからです!」妖木妃たちの感想に対して答えるように、女夷が説明を始めた。
「ミルフィーユ。通常、洋菓子の名として知られていますが、その意味は『千枚の葉』。つまり、薄く仕上げた生地を葉に見立て、数多く重ね合わせることで、サクサクとしたその食感を楽しめるという、世界に名高い銘菓です」
「知らない者はいませんな!」
「ですが、カツにすると話はまた違ってきます。何しろ、肉を紙よりも薄く押し潰しているのですから、その柔らかさは赤子でも噛み切れるほど。そんな肉を重ね合わせているのです。その柔らかさ、食感は並の肉の比ではありません!!」
「たしかに、これは肉の柔らかさとか、歯ごたえとか、そんな次元を遥かに超えている!」
「そして、更にその重ねあわせた肉と肉の間に溜まった肉汁。噛み切ったあとはどうなるか……? それはもう、ご体験して頂いたとおりです!」
「ああ、ここまで肉汁が溢れだす肉なんて、今まで食べたことがない!」
審査を務める妖木妃、白陰、ムッシュ。三人とも、もはや文句の付け所がないといった表情だ。それを見た呑雌鬼。だが、まだ何かあるように、不敵な笑みを浮かべた。それを裏付けるように女夷が説明を続ける。
「呑雌鬼氏は、更に追い打ちをかけてやる!と言っておられます」女夷がそう言うと、一人の妖怪が両手に何やら持って、呑雌鬼の前にやってきた。手にした物を受け取る呑雌鬼。
それは、一足の白いショートブーツ。そう、優里が生前履いていた、戦闘用のショートブーツであった。
呑雌鬼は、鍋を片付けたコンロの前に立つと、助手に火を付けさせた。炎を弱火に調整すると、手にしたブーツを逆さに持ち直し、つまり履き口を下に向け、その中を火で炙り始めた。
しばらく炙り続け、ブーツの内部が熱くなったのを見計らうと、再び上下をひっくり返し、納得したように微笑んだ。
「奴は、一体……何をしているんだ!?」誰もが呑雌鬼の行動を疑った。
呑雌鬼は調理台の上にブーツを並べると、燗につけた酒を、履き口から波々と中へ注ぎ込む。
「ブ……ブーツに酒を注ぐだと!? 狂っているのか、奴は!?」
そんな驚きの声を他所に、その一足のブーツを妖木妃たちの元へ運ばせた。
「『ブーツ酒』です!試してみてください。と呑雌鬼氏は仰ってます」
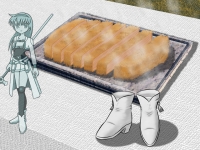
妖木妃とムッシュはそれぞれブーツを手にとり、口元へ運んだ。履き口から溢れる酒から、ハッキリと鼻に突く異臭が感じ取れる。「なるほど、そういうことですか!」ムッシュはそう呟くと、その酒を口の中に含んだ。眼を閉じ、全神経を口内に集中させ、その真意を確かめる。そして静かに飲み干すと、ニヤリと微笑んだ。
「妖木妃殿、何も言わず……騙されたと思って確かめてごらんなさい!」ムッシュは妖木妃にそう告げる。その言葉に妖木妃は、恐る恐るブーツの中の酒を口へ含んだ。
「な……なんと!?」打って変わったように、驚きとも喜びとも取れる顔をする妖木妃。そして今度は、一切の迷いなく、再び酒を口の中へ流し込んだ。
「お……、驚いた! こんなに美味い酒は、過去…数える程しか飲んだことがない!」
「面白いですな!酒の中に溶け込んだ、蒸せたような異臭。まさか、これがそんなに酒を美味くするとは!? この異臭は、白い妖魔狩人の足のアレですな!」ムッシュの言葉に呑雌鬼はコクリと頷いた。
「どんな美少女でも長時間ブーツを履いていれば、かなり足が蒸れるものです。当然、ブーツの中の臭いは相当なものでしょう。しかもソレは、熱することで更に臭気が強くなる」
「なるほど、ブーツの中を火で炙ったのは、その為か……!?」
「そんな鼻を突くような異臭ですが、日本酒と相性は抜群です。例えるなら、日本古来の食べ物『クサヤの干物』。アレなんか、酒の肴には最高ですよね。このブーツ酒は、炙ったクサヤを、熱燗にそのまま漬け込んだものと思っていただければ、理解しやすいでしょう!!」女夷は嬉々としながら、呑雌鬼の言葉を代弁していった。
「たしかにこれは、してやられたわ!」女夷の説明を聞きながら、妖木妃は、ただ、ただ、感心するだけであった。
「さぁ、ここまでは全く互角の勝負。トリ(最後)を務めるのは、正体不明の謎の仮面妖怪……、ミスターW⊥(ヴァイテ)~っ!!」女夷の紹介に、W⊥は軽く頭を下げる。
ここで驚くべきことは、女夷はまったく噛んでおらず、いつの間にか滑舌良い進行ができるようになっていたことだ。もっとも、その事は誰も気づいていないが・・・。
今まで通り、調理台の前に手押しワゴンが運ばれる。これもワゴンの上には大皿があり、中身を隠すようにドームカバーで蓋をされている。
助手の妖怪たちが皿ごと調理台へ運ぼうとすると、ミスターW⊥はそれを拒み、妖木妃たちの長テーブルを指差した。どうやら、そのまま御膳に運べということらしい。
大皿はそのまま長テーブルに置かれ、ドームカバーが取り外された。
「おおっ!?」思わず声を上げる妖木妃たち。
皿の上には、丸々と膨れ上がり、香ばしい焼き目のついた、巨大なシューが乗っていた。
「こ…これは、もしかして……シュークリーム、なのか……?」目の前に置かれた物体を、不思議そうに眺める白陰。
「では、早速……料理の解説を始めさせていただきます!!」高々とした女夷の声が響き渡る。
「今、妖木妃様方の前にあるのは、お察しの通り……シュークリーム。題して……『赤い妖魔狩人の満腹シュークリーム!』です~っ!!」
「赤い妖魔狩人の……シュークリーム?」白陰の唖然とした声。
「そのようですな、よく見たらわかりますぞ」ムッシュはそう言いながら、シュークリームの部分部分を指差した。「赤い妖魔狩人の服をひん剥き、素っ裸にしたところを真上から縦に潰し、その後膨らむように焼き上げたものですな」彼の言うとおり、狐色の焼き目の間には、きめ細かい十代の肌の色が見える。そしてシューの上側には、千佳の表情がうっすらと浮かんでいた。
調理台ではムッシュの言葉に頷くミスターW⊥。そして彼は、まずは何も言わず食してみよ。と言わんばかりに、手を差し出した。
それに同意した妖木妃、白陰、ムッシュの三人。シューを引き千切り、中に詰まっているクリームを塗りつけ口の中へ運ぶ。
「こ……これは、本当にシュークリームなのか!?」
三人が驚くのも無理は無い。通常シュークリームは、口の中に入れると、シューが溶けるように崩れ、中から甘いカスタードクリームが流れ出すというもの。
だが、今食べたソレは、そのシューが溶けるどころか、まるで暴れだすかのようなワイルドな食感と、ローティーン独特の精製していないミルクのような味を主張する。さらにクリームは……と言うと、なぜか逆に弱々しく、それでいて田舎臭い……酸味のような、やや癖のある風味で、不思議なくらいシューと見事に調和していた。ソレは彼らの知っているシュークリームとはまるで違う、それでいて、それ以上の美味さを奏でるお菓子であった。
「一体どんな作り方をすると、こんな物になるのですかな?」さすがのムッシュも、解析不能といった状態だ。
それに答えるように、女夷が解説を始めた。
「シューの材料はご存知の通り、赤い妖魔狩人です。彼女を円筒に押し込み、上下から押し潰して平らにしたものを使用しました。もちろん、それだけではまだ生地が厚く硬くなるので、更に麺棒で押し広げ、ピザ生地のように遠心力を利用した引き延ばしもしております。」
「たしかにワイルドな食感ではあるが、硬いわけでなく……むしろ柔らかい」
「そして、ソレをオーブンの中に入れ、膨れるまでコンガリと焼き上げたものです」
「なんだ、まるっきり普通の調理法じゃないか!?」妖怪たちの間から、そんな声が上がった。
「たしかに調理法自体は、何の変哲もない……オーソドックスな方法です。ただ、ミスターW⊥氏は調理法そのものよりも、素材の『真の良さ』を引き出すにはどうしたらいいか? そこに細心の注意をはらったそうです」
「素材の良さ? 今までの調理師妖怪も、ソレは十分に引き出したと思うが……?」白陰がそう漏らした言葉に、ミスターW⊥は舌打ちをしながら、人差し指を目の前で振った。
「引き出す方向性が違う!と、W⊥氏は言っておられます。なぜなら、シューに浮かぶ赤い妖魔狩人の表情を見よ!と」
女夷を通したW⊥の言葉に、皆がシューに浮かぶ千佳の表情に注目した。なんと、その表情はにこやかに微笑み、いや、それどころか満面の笑みにも見える。

「ますますわからん。これは一体どういうことですかな?」
「赤い妖魔狩人は火属性の半妖。ペチャンコにし……焼き上げた程度では、完全には息の根が止まっていない、そこが狙い目でもあったということらしいです」
「ん…ん……? 話がまったく見えてこないが……?」
「今まで調理された妖魔狩人の面々は、おそらく恐怖し、悲しみ、ストレスを感じながら調理されていったことでしょう。そうすると人間は、脳内からノルアドレナリンという物質を出し、これは素材の味を僅かながら劣化させてしまいます!」
「な…なんだと!?」
「しかしW⊥氏の赤い妖魔狩人は、先ほど言った通り焼き上げた時点では、まだ辛うじて生きていました。そこである特別なクリームを、シューとなった彼女の体内に注入したのです!」
「特別なクリーム? 普通のカスタードクリームではないのか?」白陰がそう言った途端、「そうですか!何か違和感があると思ったのですが、これであのクリームの謎が解けました!」とムッシュが声を荒げた。
「どういうことだ、ムッシュ?」妖木妃が問いただす。
「あのクリーム、弱々しい風味なのに、それでいて妙に癖の強い部分も感じ取れました。それは、ある人物になんとなく似ていると思いませんかな?」
そう答えるムッシュに、妖木妃は思い当たったようにハッとした。「く……黒い妖魔狩人……!?」
「そのとおりです!」二人の会話をまとめるように、再び女夷が話しだした。
「あのカスタードクリームの中には、黒い妖魔狩人の部屋から拝借した、下着や靴下を刻んで練り上げた物を混入させているのです!」
「やはりそうか!だから、弱々しいカスタードクリームのはずなのに、どこか田舎臭い、アンモニア臭的な酸味や癖が感じ取れたのだ!?」
「そう。そして……その黒い妖魔狩人の田舎臭い、アンモニア臭のような酸味こそが、赤い妖魔狩人にとっての至高の喜び!!」女夷の説明に合わせ、W⊥が不敵に微笑む。
「そんなものを体内に注入されたら、赤い妖魔狩人はどうなると思われます? 心の底から黒い妖魔狩人を好いている彼女です。それこそ狂喜乱舞することでしょう! あの満面の笑みはその表れです! そして、人間は喜びを得るとエンドルフィンという分泌物を放出する。これは、まるで麻薬のような歓喜の旨味! つまり、これ以上無い調味料ということです!!」
「それによって、赤い妖魔狩人が本来備えていた、あのワイルドな食感と旨味を倍増させる結果となった?」
「赤い妖魔狩人の真の性質を理解し、それを引き出したからこそ、あの味になったということじゃな」これには、妖木妃も驚くしかなかった。もはや、料理の枠を超えている……と!
これで、四人の妖怪たちの料理が全てお披露目された。どれもが想像を超える料理で、とてもじゃないが、甲乙付け難い。
「どうされます? 妖木妃様……?」ムッシュがそう問いかけた。
「ハッキリ言って、どれもが凄い料理で身共たちでは決めかねますな」白陰もそう言って、頭を抱える。
すると妖木妃は思い立ったように、助手妖怪たちに料理を集まった妖怪たち全員に配るよう命じた。
「ワシたちだけでは、とても判断できん。そこで、今……この対決を見ていたお前らにも、判断をしてもらうことにした!」
妖木妃はそう言って、今見ている妖怪を指差した。そう……彼女が指定したのは、今見ている妖怪。つまり、貴方だ!!
貴方にも、審査に加わってもらいたい!
…ということで、BADENDルートの物語は、ここで中断です。
妖木妃との直接決戦において、たった一つの凛の判断ミス。
これにより、凛はもとより他の三人の妖魔狩人も、為す術もなく倒されてしまった。
「そこのお前。すぐに白陰のところへ行き、大至急、料理のできる妖怪にここへ来るように伝えよ」
妖木妃に、そう命じられた花の妖怪……女夷。元々たいした戦闘力もなく、争いごとを好まない妖怪ではあるが、同じ植物系妖怪の誼み(よしみ)である妖木妃に逆らえず、こうして日本までやってきてしまった次第である。もっとも妖木妃にとっての女夷は、ただの雑魚部下その一であり、顔と名前の一致すらしていないだろうが。
命じられたまま白陰の元へ行くと、指示に納得した白陰は調理のできる妖怪たちを選りすぐる。なんといっても妖木妃が直々に食する料理だ。不備があってはならない。
料理の知識、腕前、様々なテストを重ね、ついに彼は四人の候補者を選出した。
「で、これがお前が選んだ調理のできる妖怪たちか?」妖木妃は、眼前に並ぶ四人の妖怪たちを見渡し、その脇にいる白陰にそう尋ねた。それに対し、「はい」と頷く白陰。
「よかろう、着いて参れ。お前たちが腕を振るう材料は、すぐそこにある」
妖木妃はそう言うと、自ら先頭に立ち、白陰と四人の調理師妖怪を引き連れ、拝殿の扉を開けた。
拝殿の中で横たわる四つの人影。それは、凛、優里、千佳、瀬織の姿であった。
「そやつらは気を失っているだけで、まだ死んではおらぬ新鮮な材料じゃ。そこで、お前らの役目じゃが、各々一体ずつ持ち帰り、それぞれ得意とする調理を施し、誰の料理が一番美味いか!?料理対決をしてもらうことにする」
「おおお……」
「ただし、一つだけ条件がある。素材は全てペチャンコ、つまり押し潰してから調理すること。ワシもこう見えていい歳だ。一度押し潰して柔らかくなった料理が、今では好みじゃ。その後は、和洋中一切問わぬ。期限は三日後の正午。いいな!? 自慢の腕を奮った見事な料理をこさえてみよ」
妖木妃の言葉を聞き、四人の妖怪は凛たちのもとに集まり、それぞれ品定めを始めた。直接肌に触れ、匂いを嗅ぎ、後が残らぬように軽く舌で触れ、味覚を確かめる者もいた。
すると、一人の白く小柄な妖怪が納得したように立ち上がると、凛を指差し妖木妃と白陰の了承を求めた。無言で頷く両者。それを確かめると、そいつは凛の身体を抱え上げ、静かにその場を立ち去っていった。
残る三人の妖怪は、優里の身体をジッと見つめている。どうやら三人とも、自分の料理の材料には優里が相応しいと決めたようだ。
特に二人の妖怪。一人は真夏だというのに黒いコートを羽織い、コート以外も全身黒尽くめの出で立ちに、背中に二本の巨大包丁をX字に背負っている。もう一人は子どもと変わらぬほどの小柄で、まるでマカロンのような頭部で、しかも二頭身の身体つき。この二人は互いに睨み合ったまま、一歩も引きそうにない気配を見せていた。
そんな二人を「やれやれ……」といった雰囲気で見つめていた、無表情な白い面を被った残る一人の妖怪。彼は何も言わず二~三歩進みと、なんと、千佳の身体を指差した。「赤い妖魔狩人でいいのか?」白陰の問いに白い面の妖怪はコクリと頷き、そのまま千佳の身体を担ぎ上げ無言で去っていった。
あとは、黒尽くめと二頭身の二人の妖怪。どちらも高い戦闘力の持ち主のようで、睨み合うだけで、地鳴りが起きそうな気配がしている。そんな二人を見兼ねたように妖木妃が声を掛けた。
「欲しいものは力尽くで奪え。いつものワシならそう言うであろうが、今はあえてこう言おう。時間が惜しい、争わずに決めるがよい」
その言葉に二人は渋々頷くが、とは言ってもどのようにして決めろと?と言いたげな表情である。そこに白陰が間に入った。「仕方ない、ここは日本。日本流の平和な決着法……『ジャンケン』で決めるとしよう」
「ジャンケン……ポン!」白陰の掛け声で二人とも握りこぶしを出す。「アイコで……ショッ!」「アイコで……ショ!」と二~三回アイコが続き、最後に二本指と握りこぶし。
小さなガッツポーズを決めたのは、小柄な二頭身妖怪。彼は嬉しそうに優里の脇に立つと、驚いたことに身体の半分を占める頭が、更に膨らむように大きくなっていった。そしてガマ口のような大きな口を広げ、パクリと優里の身体を咥え込んだ。本当はそのまま丸呑みしたいのだが、そこは我慢。優里を咥えたまま、その場を立ち去っていった。
最後に残された黒尽くめの妖怪。仕方ない……といった表情で、瀬織を担ぎ上げると、そのまま霧のように去っていった。
そして三日後の正午。拝殿脇に並べられた長テーブル。白いクロスで覆われており、上座に腰掛けているのは、当然……妖木妃。妖木妃から向かって右側には、白陰。左側にはムッシュが腰掛けている。
司会進行役は、なぜか花の妖怪である女夷。マイクを持つその手は、ガタガタと震えている。
「わ・わ・わ・私の……記憶が確かならば……、こ・こ・今回……揃えられた材料、そ…そして……それを料理した対決というのは、し・し・神話……の世界、まだ……多くの神族が……、地上を支配していた……ときまで、遡らなければ……いけないはずです……」
震えたマイクに震えた声。そして、震える手で読み上げる数枚のメモ紙。
「何を言っておるのじゃ? あの娘は……?」
「ムッシュであろう? あんな物を読ませたのは!?」と白陰がムッシュに睨みを利かす。
「うむ、やはり料理対決となれば、こうでなくてはならんと思いましてな!」当のムッシュは悪びれもせず、自慢のカイゼル髭をピンと伸ばし、楽しそうにニカッ!と笑った。
そんな楽しそうなムッシュとは裏腹に、今にも卒倒しそうなくらいオロオロしっぱなしの女夷。震えながら更に進行していく。
「い・い・い・今こそ……よ・よ・よ・甦れ・れ・れ……、伝説の……て・て・鉄人……、も…もとい、鉄の妖怪……。ア・ア・ア・アイアン……イ~~~ビル~~~ッ!!」
それが合図となったのか、拝殿前の参道を大量の白煙(ドライアイス?)が、覆い尽くす。そして、その白煙の中から四人の影が姿を現した。

「こんな臭い演出、やる必要があるのか?」さすがの妖木妃も苦笑い。
「ま……まずは、一人目。世界を股にかけて食べ歩く、流れの料理人……! 某特務機関超能力支援研究局(通称バ◯ル)所属のレベル7テレポーターから、『りゅりょりゅにゅ‥‥ごめん、噛んでしもた!』とまで言わさせた、変態妖怪……るりょけん!!」
最初の紹介で登場したのは、真っ先に凛を担いで去っていった妖怪。真っ白な毛に覆われた、丸々とした流線形。つまりアザラシの姿をした、強いのか?弱いのか?まるで見当のつかない。こいつは妖木妃に手を振りながら、調理台の前についた。
「あんなの、ワシの部下におったか?」怪訝そうな眼で眺める妖木妃。
「つ…つ……続きまして、調理の腕も然ることながら、ダンジョン探索が三度の飯より大好き! 別名黒き料理師、ビーター妖怪……霧斗!!」
現れたのは、あのコートを含めた頭の先から足の先まで全身黒尽くめの妖怪。その素顔はまだ十代少年の面影を残し、今風のイケメン顔であった。霧斗は礼儀正しく妖木妃に一礼すると、次の調理台の前についた。
「ビーター妖怪? 噂では聞いたことがある。なんでも神獣と互角に戦えるとか。そうか、コヤツのことであったか!」妖木妃はそう言って、ニヤリと微笑む。
「つ・つ・次は……、絵の前にいるのは、すべてオレの餌!人も獣も、その気になれば鯨でさえ一呑み! ま・ま・丸呑み妖怪……呑雌鬼(どんしおに)!!」
この紹介で現れたのは、マカロンのような頭の小柄な二頭身妖怪。呑雌鬼は妖木妃の前を通る際、大きな口で歯を剥きだしたままニカッ!と笑って、調理台についた。
「あーっ、知っているぞ……コイツ! たしかに以前インドで、象を一頭丸呑みしていたのを、見たことがある!!」白陰が思い出したように、指を指した。
「さ・最後は……、料理も獣化も状態変化も、そして固めでも全てお手の物!いつの間にか一味に加わっている謎の仮面妖怪……ミスターW⊥(ヴァイテ)!!」
シルクハットに黒いマント。千佳を連れ去った時以上にお洒落な出で立ちで現れたのは、真っ白の無表情な面を付けた男。妖木妃に軽く会釈すると、静かに調理台についた。
「ほぉ!なんとなくですが、コヤツからはアジアではなく、我輩の好きな欧州の匂いがしますな!」ムッシュの嬉しそうな声。
「ほ・ほ・本日……、以上四名が……腕を振るった料理を、ひ・ひ・披露……致します!! し・し・し・審査員の皆様方、公平な審査、よろしくお願いいたします……!!」
女夷の言葉に再び四人が、妖木妃たちに向かって会釈した。
「し…進行は引き続き……私、女夷がさせていただきます……。な・なお……、調理された妖怪の方々の中には、人前でお話をされるのを苦手としていらっしゃる方もおられるようなので、料理の説明なども全て、私がさせていただきます……。では、最初は……るりょけん氏から……」
女夷はそう言うと参道に向かって振り返り、そこで待機している数名の妖怪たちに合図を送った。
すると、二~三人の妖怪たちが、手押しワゴンを運んでくる。ワゴンの上には、人ひとり横たわれそうな大きさの銀の角皿が乗っていた。ワゴンは妖怪るりょけんの調理台の前に止まると、角皿が調理台へ移された。皿には蓋が掛けてあるので、まだ中身はわからない。
妖怪たちの手によって、蓋が取り払われる。
「おおっ!?」妖木妃、白陰、ムッシュ、そして周りで見ている大勢の妖怪たちの、驚きの声があがった。
角皿に寝かせるように乗せられているもの。それは、横に厚さ5ミリメートル程まで薄く押し潰された、若三毛凛の姿であった。
「ほぅ、一番目から黒い妖魔狩人の料理か!?」少し意外だったような口調の妖木妃。
「見たところ、たしかにペチャンコにはなっているが、それ以外……何も調理されていない、まるっきり生(なま)のように見受けられるが……?」
白陰の言うとおり、角皿に乗っている凛は戦闘服を着たまま綺麗に押し潰されているが、それ以外は生きていても不思議ではないほど無傷な状態であり、どう見ても手を加えられた様には見えない。
「いや、アレは結構……良い仕事をしているようですぞ!」だが、ムッシュだけは何かを見抜いたようにそう呟いた。それを耳にした妖怪るりょけん。わかってくれたか!と言わんばかりに、ニヤリと微笑んだ。
るりょけんは刺身包丁を手に取ると、凛の左足の脛の部分を、一口大の大きさに三~四つほど切り分けた。そしてソレを一枚ずつ小皿に乗せると、助手の妖怪に長テーブルまで運ぶように指示を出した。
命じられたまま、小皿を妖木妃、白陰、ムッシュの前に置く。
「まずは、一口……味見をしてみろ、ということですかな?」ムッシュはそう言うと、箸で切り身を摘むと、そのまま口まで運んだ。妖木妃、白陰も後に続く。
モグ……モグ……モグ……
「ほぅ!」「おおっ!」「うむ、悪くない!」それぞれから笑みが溢れる。
「え・・え……っと、説明させて頂きますと、それは『黒い妖魔狩人の一夜干し』だそうです……」女夷がるりょけんの言葉を、改めてマイクを通して語りだした。
「まずは、黒い妖魔狩人を重さ五百キログラムの鉄の重石で押し潰します。程よく均等に押し潰されたのを確認したら、今度は黄金のロールプレス機で圧延いたします」
「ロールプレス機……?あの、回転するローラーを使った機械か? わざわざそんなもので……?」
「ロールプレス機を使った理由は、より薄く……そして、より均等にしたかったこともありますが、一番重要なのは、コレを手に入れるため!……だそうです」女夷がそう説明すると、るりょけんは容量1リットル程のガラス製の瓶を、高々と上げた。瓶の中には、半透明の黄色染みたトロリとした液体が入っている。
「瓶の中身は、黒い妖魔狩人の汗や分泌液、そして尿などが程良く混ざり合った純粋な体液です。ロールプレス機の利点は、このように身体の隅々から体液を絞り取ることができるのです!」
「なるほど、一昔前の洗濯機に付いていたローラーと同じですな!」
「ペラペラになった身体を風通しのよい日陰で干しながら、その体液を何度も塗り続け、味を染み込ませるそうです!」
「なるほど!本来ならば、土臭くて味気ない十代前半のガキなのに、それによって適度な塩分や酸味によってほのかな甘味が引き出され、この美味さになっているのか!?」
さすがの妖木妃も口元が緩まずにはいられない。
「えっと……、それで驚いてもらっては困る。本番はこれからだと、るりょけん氏は申しております!!」
「なんだと、この料理で終わりじゃないのか!?」
女夷の言葉に、誰もが再び調理台に注目した。皆の注目の中、妖怪るりょけんは助手の妖怪に指示を送る。しばらくすると二~三人の妖怪たちが、高さ50センチメートル直径1.5メートル程の円筒のような物を運んできた。
「七輪か!?」白陰の言葉の通り、それは通常より大きめの七輪。中には赤々と燻っている炭が積み込まれてあり、充分熱せられた、金網が乗せてある。
るりょけんは炭火の状態を確認すると、ペラペラと風になびく凛の身体を、金網の上に静かに乗せた。
パチッ…パチッ…と炭が弾ける音と共に、香ばしい匂いが漂いだした。ピラピラに伸びきった凛の身体が、熱を帯びてくるとジリジリと僅かながら縮みだす。そして、頃合いを見て裏表ひっくり返す。今まで火に炙られていた面が、少しだけ狐色に焼き目が付いていた。

更にいい匂いが漂い出した頃、るりょけんは凛の身体を引き上げ、調理台の皿の上に乗せ直した。
「えっと……、ここで大事なのは、決して焼き過ぎないことだそうです。全体を軽く炙るだけで、適度に温まる程度に火が通るのが、一番良いとのことです」
女夷の解説に、妖怪るりょけんは大きく頷いた。そして、先程と同じように一口大の大きさに切り分けていく。
妖木妃たちの元へ運ばれた切り身の他に、今度は小皿に入った濃い橙色の液体が、一緒に配られた。
「炙った切り身を、その皿のタレに付けて食べて欲しいそうです!」
言われた通りに切り身にタレをつけ、口へ運ぶ。
「おおっ!なんとっ!!?」「こ…これは凄いっ!」「うむ、悪くないどころか、これは絶品ですな!!」先程以上の歓喜の声を上げ、目を丸くし、嬉々とした表情の妖木妃たち。
「温めたことで切り身の甘みが遥かに増し、更に焼き目の香ばしさが食欲を倍増させる。そして……問題は、このタレだっ!?」
誰もが同様に口走る問いに、るりょけんはボソボゾと女夷に返答を命じる。
「そのタレは先程の体液をベースにし、酒とみりんで味を整え、紅葉おろしを加えたものだそうです!」
「なるほど! 同じ黒い妖魔狩人の体液ですか!?だから違和感無く切り身と調和するのですな。そして紅葉おろしの辛味が、さらに切り身の甘みを引き出す!! 見事な仕事ですぞ!」
さすがのムッシュも、まるで感服したかのように満面の笑みを浮かべ、自身の髭を弄くっている。
「素晴らしい。できることなら、この干物の太腿の部分を味わってみたいが……」
妖木妃がそう呟くのを見計らったように、もう一品の皿が前に差し出された。「もしや?」妖木妃は調理台にいる妖怪るりょけんをみると、彼は腿の部分を切り取った干物をチラリと見せた。
「一番軟らかく、一番素材の味が確かな、内腿の部分だそうです」助手妖怪が、さり気なく付け加えた。
出された内腿の切り身にタレをつけ、口へ運ぶ。
「ぉぉぉぉぉぉぉ………」妖木妃は、もはや言葉を忘れそうになった。爽やかな甘みと塩っぱさと、癖のある酸味が奏でる見事なハーモニー。それは至高と呼ぶに相応しい、旨味の世界であった。
「で…では、次の方に進みます! 次は人間退治だけでなく、神獣まで成敗する最強の妖怪剣士、霧斗氏です!」
女夷の掛け声が終わると、またも手押しワゴンが運ばれ、霧斗の調理台の前に止まった。ワゴンの上にはトラックのタイヤを重ねたような、大きな蒸籠が乗っている。
「今度は、蒸し料理か?」思わず問いかける白陰に「いや、蒸気が吹き出していないところを見ると、蒸籠はただの演出上の飾りでしょうな!」とムッシュが答えた。
数人が蒸籠を調理台の上に乗せると、ニヤリと微笑む霧斗が、勢いよく蓋を取り外した。
眼に飛び込んで来たのは、鮮やかなピンク……いや、桜色と、清々しい緑色! それは桜色の丸まった物体を、大きな緑色の葉で包んだものであった。
「柏……もち……?」そう呟く白陰。「いや、あの葉は柏では無い。アレは桜の葉……」自身が植物系妖怪であるため、植物に詳しい妖木妃がそう返した。
「そ……そ、そうです! 霧斗氏の作られた料理は、妖怪桜の葉で包んだ、『青い妖魔狩人(棚機瀬織)の桜餅』です!!」
「おおおっ!!」女夷の説明に、多くの妖怪たちから歓声が上がる。
たしかに言われてみると、大きな桜の葉のすぐ下には、厚さ1~2センチ程の平たい餅のような物が二つ折りにされ、その間には見るからに甘そうなこし餡が収まっている。
「では、あの桜色の平たい餅が、青い妖魔狩人なのか!?」「そのようですな、良くご覧になるといい。餅の端にグルグルと眼を回した青い妖魔狩人の顔が見える」
そのような会話が進む中、霧斗は背中に背負った大きな包丁を一本抜き取ると、鮮やかな太刀筋で、桜餅を数十等分に切り分けた。そのうちの三切れを皿に取り分けると、助手妖怪に妖木妃たちのテーブルに運ばせた。
テーブルに並ばれた桜餅の切り身。ほのかな桜色と微かな桜の葉の香りが、食欲を誘う。
「ほぅ。たしかによく見ると、餅のように見えるが、間違いなくペチャンコになった小娘じゃ。しかも生ではなく、焼き目が入っておるな!」
妖木妃はそう呟くと、黒文字(和菓子用の楊枝)で更に小さく切り分け、口へ運んだ。
口へ入れた途端、桜の花の甘い香りが口内に広がる。柔らかくなった餅を歯茎や舌で噛み潰していくと、コクのある甘さのこし餡が溶けるように流れ出る。
「うむ、これは見事じゃ!」思わず妖木妃が唸った。
「さ……さて、ここでこの桜餅の調理方法を説明いたします!!」女夷が自身に注目を向けるように金切り声を上げた。
「さ・最初にお話したとおり、この料理のメイン食材は、青い妖魔狩人です! まず捉えた青い妖魔狩人に、十年ほど寝かせた『さくらんぼ酒』を飲ませます。未成年でアルコールに弱い青い妖魔狩人はすぐに酔いが回り、眼を回してひっくり返りました。」
「なるほど。頬も含め、全身が桜色なのは酔っ払ったせいか!」
「更に、グデグデになった青い妖魔狩人を、これまた桜の木で作った大きな枠の中に寝かしつけ、全身が浸るまで『さくらんぼ酒』を注ぎ込みます。そして、その身体におよそ200キログラム程の重しを乗せ、ゆっくりとジワジワ押し潰していき、そのまま丸一日置いておきます。そうすることによって、さくらんぼ酒がじっくりと、身体に染みこまれていくわけです」
「元々青い妖魔狩人は色白だったから、だからここまで綺麗な桜色に仕上がったわけだ!!」
「後は、ペチャンコになった身体を吊るし干しにして、余分なアルコールを抜いていきます。そして再び麺棒で厚さ1~2センチほどまで押し伸ばしたあと、鉄板の上で軽く両面を焼き上げ、焼き目と香ばしい香りを付けます」
「見た目は若いが、見事に和菓子の調理法を身につけているな!」
「最後に身体の中心にこし餡を乗せ二つ折りにし、そのまま妖怪桜の葉で包んで完成です!!」

女夷が説明を終えると、盛大な拍手が霧斗へ送られた。大げさに騒ぐわけでなく、回りに軽く会釈をし、拍手に答える霧斗。
「だが、それだけではあるまい!?」そんな歓声を遮るように、妖木妃が一喝した。
「この美味さ、それだけではあるまい。おそらくその秘密は……餡! そう、餡にあると思えるのだが!?」
そんな妖木妃を後押しするように、ムッシュが更に付け加えてきた。「妖木妃殿の仰るとおり、問題は餡ですな! 通常、和菓子の餡は、甘味を引き立てるために、隠し味に『塩』を一摘み入れると聞きます。ですが、この餡は甘味だけでなく……深い独特なコクのようなものも感じ取れる。おそらく隠し味に使ったのは、塩では無いのではないかと……?」
妖木妃とムッシュの問いに、霧斗は不敵な笑みを浮かべた。それは剣士が最高の好敵手に出逢えたような、そんな含みを込めた笑みだ。
「さすがは、おふた方……。と霧斗氏は申しております」女夷がそう述べると、更に霧斗が女夷に耳打ちをする。
「たしかに隠し味に塩は使用せず、ある特別な物を使ったそうです。その、ある特別な物とは……『青い妖魔狩人が身に着けていた下着』!!」
「し……下着……だと?」白陰が驚きの声を漏らす。
『身に着けていたパンツやブラなどの下着を寸胴鍋に入れ、たっぷりの水を注ぎます。それを火に掛け、八割以上の水が蒸発するまで存分に煮込みます。すると僅かに残った湯は、下着のエキスと旨味が凝縮された、味の濃いダシ汁になっているというわけです!」
「おおおっ!!?」
「そのダシ汁を十分に冷ましたあと餡に注ぎ込み、しっかりと練り上げるんだそうです!」
「なるほど! 下着に染み込んだ『汗』が塩分の役目になり、同様に染み込んでいる他の匂いや分泌物が、あの独特のコクになったというわけですな!」
そう言いながら、感心のあまり何度も納得したように頷くムッシュ。
「うむ、文句ない! 見事じゃ……霧斗よ!」妖木妃も讃美の言葉を述べた。
「では、では……、次の方に参ります。次は人間を丸呑みすること数百年!丸呑み世界一を誇る、妖怪……呑雌鬼氏です!」
紹介の後は、今まで通りワゴンが運ばれる。ワゴンの上には大きな丸皿が乗っており、中身を隠すように、半径50センチ程のドームカバーで蓋をしてある。今度は調理台に移す前に、呑雌鬼がドームカバーを外し、中身を披露した。
そこには、縦20センチ・横40センチ・厚さ5センチほどの、まるでコピー用紙を数百枚ほど重ねたような、そんな白っぽい塊が置いてあった。
「なんだ……あれは!?」
周りがどよめく中、呑雌鬼の大きな口が、勝ち誇ったようにニヤリと笑う。そして、コピー用紙の一番上の紙をめくり上げるかのように、その白い塊の一番上の辺りを、ペラリとめくり上げた!
な・な・な……なんと! めくり上げられた紙のような薄い物には、半開きの口に、グルグルと眼を回し、呆けた『優里』の顔があった!!
「な、なんだと……? もしかして、あの白い塊は白い妖魔狩人を折り畳んだ物なのか……!? だ・だが……あの薄さはなんだ!? どう見ても……紙よりも薄いぞ!?」あまりの驚きに、思わず立ち上がってしまった白陰!
いや、白陰だけではない。周りにいる妖怪たち全てが、驚きを隠せなかった。
「え……えっと、皆さんが思っておられる通り、ここにあるのは、極限まで薄く伸ばしてから折り畳んだ、白い妖魔狩人だそうです!」
女夷の解説が始まると、誰もが息を飲んだように静まりかえる。
「まず、捉えた白い妖魔狩人をうつ伏せに固定し、上部から『ランマ』を使って、押し潰すところから始めます」
「ランマって……!?」「ほ・ほれ……、道路工事なんかで、ダダダダダッ!!ってホッピングみたいに上下振動し、アスファルトを押し固める機械だよ!」「あ…あんなんでか!?」
「あくまでも適度に押し潰すのが目的なので、別にランマじゃなくてもいいそうですが、激しい振動で、正気を失ったようにヘロヘロに悶えていく妖魔狩人の姿が面白いので、あえてソレを使ったそうです!」と、周りの声に答えるように、女夷が説明に補填をした。
「厚さ数センチメートルまで押し潰したら、それを大きな金パットに入れ、切り刻んだパイナップルと一緒に一晩漬け込みます。そうすることで、肉が更に柔らかくなるそうです!
翌日、のし台の上に妖魔狩人を平らに敷き、彼女の足元から麺棒を手前に巻きつけ、体重を乗せて転がしていきます。一通り転がしたあと麺棒から引き離し、再び足元から巻きつけ、また同じように押し転がしていきます」
「ふむふむ、うどんを打つのと同じ要領か!」
「ポイントは、生地同士が引っ付き合わないようにすることと、押し潰すことで中のエキスが外へ逃げないようにするために、特殊な和紙を間に挟んでおくことです。そうして、この作業を四~五十回ほど繰り返します!!」
「し……四~五十回だと!?」
「丁寧に時間を掛けて作業することで、このように裏面が透けて見えそうなくらい、すなわち……厚さ1/100ミリメートルまで薄く押し延ばすことができるのです!!」
「た……、たしかに、職人技だ……!?」改めてその薄さを見て、誰もが驚愕を隠せない。
「そして、薄く延びた生地を20センチごとに折り畳んでいきます。こうして仕込んだのが、今……目の前にあるコレ、白い妖魔狩人の『ミルフィーユ・カツ』です!」
「み…ミルフィーユ・カツ!?」
「今からコレにパン粉をまぶし、油で揚げて、仕上げに入ります」
女夷の説明が終わると同時に、優里の身体は調理台の上へ運ばれた。台の上には金パットが置かれており、中にはたっぷりのパン粉が敷き詰められている。溶き卵とパン粉、交互に塗り固められていく優里。
その傍らで、他の助手妖怪たちが大きなコンロを用意し、大鍋で大量の油を沸かしている。
カツ(優里)の準備を終えると、呑雌鬼は自らの指を油に突っ込み、油温を確認する。「うむ!」そう頷くと、助手妖怪たちにカツを鍋に投じるように命じた。
ジュワァァァァァッ!! 油が弾けると同時に、香ばしい匂いが辺りに漂いだす。底に沈んでいたカツも、ゆっくりと浮き上がってきた。呑雌鬼は、それを菜箸で突きながら、時折ひっくり返し、満遍なく火を通していく。
十数分経ち、油の弾け具合から頃合いを見定めると、呑雌鬼は大きなザーレン(油こし)で、カツを掬い上げた。そして調理台の上のまな板の上に乗せる。
濛々と上がる湯気と、香ばしい匂いを放つ大きなカツ。呑雌鬼は大きな包丁を両手で握り、ザクッ!ザクッ!と均等に切り分けていく。
そして、ついに妖木妃たちのテーブルに、切り分けられたカツが並べられた。溢れ出る肉汁と脂の甘い匂い。それだけで、ご飯三杯はいけそうなくらい、いい匂いだ。
「まずはソースも何も付けず、そのままガブリと齧り付いてください!」女夷の言葉に、カツを摘み、そのまま口へと運ぶ。
ガブッ! 一噛み。たった一噛みで、口の中に大量の肉汁が崩壊したダムのように溢れだした。一気に肉の甘味が口の中に広がっていく。
「おおおっ!なんという……美味さだ!!」思わず歓喜の声を上げる白陰。
「いや、たしかに美味いが、驚くべきことはそれだけではありませんぞ!」と言葉をつけ加えるムッシュ。
「うむ、驚きべきことは、この肉の柔らかさだ!口内にちょっと圧力をかけるだけで、切れ目から解れるかのように、簡単に食いちぎれる!!」あの妖木妃ですら、喜びのあまり、冷静さを欠いている。
「美味しさの秘訣は、ミルフィーユ・カツとして仕上げたからです!」妖木妃たちの感想に対して答えるように、女夷が説明を始めた。
「ミルフィーユ。通常、洋菓子の名として知られていますが、その意味は『千枚の葉』。つまり、薄く仕上げた生地を葉に見立て、数多く重ね合わせることで、サクサクとしたその食感を楽しめるという、世界に名高い銘菓です」
「知らない者はいませんな!」
「ですが、カツにすると話はまた違ってきます。何しろ、肉を紙よりも薄く押し潰しているのですから、その柔らかさは赤子でも噛み切れるほど。そんな肉を重ね合わせているのです。その柔らかさ、食感は並の肉の比ではありません!!」
「たしかに、これは肉の柔らかさとか、歯ごたえとか、そんな次元を遥かに超えている!」
「そして、更にその重ねあわせた肉と肉の間に溜まった肉汁。噛み切ったあとはどうなるか……? それはもう、ご体験して頂いたとおりです!」
「ああ、ここまで肉汁が溢れだす肉なんて、今まで食べたことがない!」
審査を務める妖木妃、白陰、ムッシュ。三人とも、もはや文句の付け所がないといった表情だ。それを見た呑雌鬼。だが、まだ何かあるように、不敵な笑みを浮かべた。それを裏付けるように女夷が説明を続ける。
「呑雌鬼氏は、更に追い打ちをかけてやる!と言っておられます」女夷がそう言うと、一人の妖怪が両手に何やら持って、呑雌鬼の前にやってきた。手にした物を受け取る呑雌鬼。
それは、一足の白いショートブーツ。そう、優里が生前履いていた、戦闘用のショートブーツであった。
呑雌鬼は、鍋を片付けたコンロの前に立つと、助手に火を付けさせた。炎を弱火に調整すると、手にしたブーツを逆さに持ち直し、つまり履き口を下に向け、その中を火で炙り始めた。
しばらく炙り続け、ブーツの内部が熱くなったのを見計らうと、再び上下をひっくり返し、納得したように微笑んだ。
「奴は、一体……何をしているんだ!?」誰もが呑雌鬼の行動を疑った。
呑雌鬼は調理台の上にブーツを並べると、燗につけた酒を、履き口から波々と中へ注ぎ込む。
「ブ……ブーツに酒を注ぐだと!? 狂っているのか、奴は!?」
そんな驚きの声を他所に、その一足のブーツを妖木妃たちの元へ運ばせた。
「『ブーツ酒』です!試してみてください。と呑雌鬼氏は仰ってます」
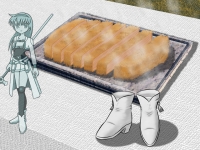
妖木妃とムッシュはそれぞれブーツを手にとり、口元へ運んだ。履き口から溢れる酒から、ハッキリと鼻に突く異臭が感じ取れる。「なるほど、そういうことですか!」ムッシュはそう呟くと、その酒を口の中に含んだ。眼を閉じ、全神経を口内に集中させ、その真意を確かめる。そして静かに飲み干すと、ニヤリと微笑んだ。
「妖木妃殿、何も言わず……騙されたと思って確かめてごらんなさい!」ムッシュは妖木妃にそう告げる。その言葉に妖木妃は、恐る恐るブーツの中の酒を口へ含んだ。
「な……なんと!?」打って変わったように、驚きとも喜びとも取れる顔をする妖木妃。そして今度は、一切の迷いなく、再び酒を口の中へ流し込んだ。
「お……、驚いた! こんなに美味い酒は、過去…数える程しか飲んだことがない!」
「面白いですな!酒の中に溶け込んだ、蒸せたような異臭。まさか、これがそんなに酒を美味くするとは!? この異臭は、白い妖魔狩人の足のアレですな!」ムッシュの言葉に呑雌鬼はコクリと頷いた。
「どんな美少女でも長時間ブーツを履いていれば、かなり足が蒸れるものです。当然、ブーツの中の臭いは相当なものでしょう。しかもソレは、熱することで更に臭気が強くなる」
「なるほど、ブーツの中を火で炙ったのは、その為か……!?」
「そんな鼻を突くような異臭ですが、日本酒と相性は抜群です。例えるなら、日本古来の食べ物『クサヤの干物』。アレなんか、酒の肴には最高ですよね。このブーツ酒は、炙ったクサヤを、熱燗にそのまま漬け込んだものと思っていただければ、理解しやすいでしょう!!」女夷は嬉々としながら、呑雌鬼の言葉を代弁していった。
「たしかにこれは、してやられたわ!」女夷の説明を聞きながら、妖木妃は、ただ、ただ、感心するだけであった。
「さぁ、ここまでは全く互角の勝負。トリ(最後)を務めるのは、正体不明の謎の仮面妖怪……、ミスターW⊥(ヴァイテ)~っ!!」女夷の紹介に、W⊥は軽く頭を下げる。
ここで驚くべきことは、女夷はまったく噛んでおらず、いつの間にか滑舌良い進行ができるようになっていたことだ。もっとも、その事は誰も気づいていないが・・・。
今まで通り、調理台の前に手押しワゴンが運ばれる。これもワゴンの上には大皿があり、中身を隠すようにドームカバーで蓋をされている。
助手の妖怪たちが皿ごと調理台へ運ぼうとすると、ミスターW⊥はそれを拒み、妖木妃たちの長テーブルを指差した。どうやら、そのまま御膳に運べということらしい。
大皿はそのまま長テーブルに置かれ、ドームカバーが取り外された。
「おおっ!?」思わず声を上げる妖木妃たち。
皿の上には、丸々と膨れ上がり、香ばしい焼き目のついた、巨大なシューが乗っていた。
「こ…これは、もしかして……シュークリーム、なのか……?」目の前に置かれた物体を、不思議そうに眺める白陰。
「では、早速……料理の解説を始めさせていただきます!!」高々とした女夷の声が響き渡る。
「今、妖木妃様方の前にあるのは、お察しの通り……シュークリーム。題して……『赤い妖魔狩人の満腹シュークリーム!』です~っ!!」
「赤い妖魔狩人の……シュークリーム?」白陰の唖然とした声。
「そのようですな、よく見たらわかりますぞ」ムッシュはそう言いながら、シュークリームの部分部分を指差した。「赤い妖魔狩人の服をひん剥き、素っ裸にしたところを真上から縦に潰し、その後膨らむように焼き上げたものですな」彼の言うとおり、狐色の焼き目の間には、きめ細かい十代の肌の色が見える。そしてシューの上側には、千佳の表情がうっすらと浮かんでいた。
調理台ではムッシュの言葉に頷くミスターW⊥。そして彼は、まずは何も言わず食してみよ。と言わんばかりに、手を差し出した。
それに同意した妖木妃、白陰、ムッシュの三人。シューを引き千切り、中に詰まっているクリームを塗りつけ口の中へ運ぶ。
「こ……これは、本当にシュークリームなのか!?」
三人が驚くのも無理は無い。通常シュークリームは、口の中に入れると、シューが溶けるように崩れ、中から甘いカスタードクリームが流れ出すというもの。
だが、今食べたソレは、そのシューが溶けるどころか、まるで暴れだすかのようなワイルドな食感と、ローティーン独特の精製していないミルクのような味を主張する。さらにクリームは……と言うと、なぜか逆に弱々しく、それでいて田舎臭い……酸味のような、やや癖のある風味で、不思議なくらいシューと見事に調和していた。ソレは彼らの知っているシュークリームとはまるで違う、それでいて、それ以上の美味さを奏でるお菓子であった。
「一体どんな作り方をすると、こんな物になるのですかな?」さすがのムッシュも、解析不能といった状態だ。
それに答えるように、女夷が解説を始めた。
「シューの材料はご存知の通り、赤い妖魔狩人です。彼女を円筒に押し込み、上下から押し潰して平らにしたものを使用しました。もちろん、それだけではまだ生地が厚く硬くなるので、更に麺棒で押し広げ、ピザ生地のように遠心力を利用した引き延ばしもしております。」
「たしかにワイルドな食感ではあるが、硬いわけでなく……むしろ柔らかい」
「そして、ソレをオーブンの中に入れ、膨れるまでコンガリと焼き上げたものです」
「なんだ、まるっきり普通の調理法じゃないか!?」妖怪たちの間から、そんな声が上がった。
「たしかに調理法自体は、何の変哲もない……オーソドックスな方法です。ただ、ミスターW⊥氏は調理法そのものよりも、素材の『真の良さ』を引き出すにはどうしたらいいか? そこに細心の注意をはらったそうです」
「素材の良さ? 今までの調理師妖怪も、ソレは十分に引き出したと思うが……?」白陰がそう漏らした言葉に、ミスターW⊥は舌打ちをしながら、人差し指を目の前で振った。
「引き出す方向性が違う!と、W⊥氏は言っておられます。なぜなら、シューに浮かぶ赤い妖魔狩人の表情を見よ!と」
女夷を通したW⊥の言葉に、皆がシューに浮かぶ千佳の表情に注目した。なんと、その表情はにこやかに微笑み、いや、それどころか満面の笑みにも見える。

「ますますわからん。これは一体どういうことですかな?」
「赤い妖魔狩人は火属性の半妖。ペチャンコにし……焼き上げた程度では、完全には息の根が止まっていない、そこが狙い目でもあったということらしいです」
「ん…ん……? 話がまったく見えてこないが……?」
「今まで調理された妖魔狩人の面々は、おそらく恐怖し、悲しみ、ストレスを感じながら調理されていったことでしょう。そうすると人間は、脳内からノルアドレナリンという物質を出し、これは素材の味を僅かながら劣化させてしまいます!」
「な…なんだと!?」
「しかしW⊥氏の赤い妖魔狩人は、先ほど言った通り焼き上げた時点では、まだ辛うじて生きていました。そこである特別なクリームを、シューとなった彼女の体内に注入したのです!」
「特別なクリーム? 普通のカスタードクリームではないのか?」白陰がそう言った途端、「そうですか!何か違和感があると思ったのですが、これであのクリームの謎が解けました!」とムッシュが声を荒げた。
「どういうことだ、ムッシュ?」妖木妃が問いただす。
「あのクリーム、弱々しい風味なのに、それでいて妙に癖の強い部分も感じ取れました。それは、ある人物になんとなく似ていると思いませんかな?」
そう答えるムッシュに、妖木妃は思い当たったようにハッとした。「く……黒い妖魔狩人……!?」
「そのとおりです!」二人の会話をまとめるように、再び女夷が話しだした。
「あのカスタードクリームの中には、黒い妖魔狩人の部屋から拝借した、下着や靴下を刻んで練り上げた物を混入させているのです!」
「やはりそうか!だから、弱々しいカスタードクリームのはずなのに、どこか田舎臭い、アンモニア臭的な酸味や癖が感じ取れたのだ!?」
「そう。そして……その黒い妖魔狩人の田舎臭い、アンモニア臭のような酸味こそが、赤い妖魔狩人にとっての至高の喜び!!」女夷の説明に合わせ、W⊥が不敵に微笑む。
「そんなものを体内に注入されたら、赤い妖魔狩人はどうなると思われます? 心の底から黒い妖魔狩人を好いている彼女です。それこそ狂喜乱舞することでしょう! あの満面の笑みはその表れです! そして、人間は喜びを得るとエンドルフィンという分泌物を放出する。これは、まるで麻薬のような歓喜の旨味! つまり、これ以上無い調味料ということです!!」
「それによって、赤い妖魔狩人が本来備えていた、あのワイルドな食感と旨味を倍増させる結果となった?」
「赤い妖魔狩人の真の性質を理解し、それを引き出したからこそ、あの味になったということじゃな」これには、妖木妃も驚くしかなかった。もはや、料理の枠を超えている……と!
これで、四人の妖怪たちの料理が全てお披露目された。どれもが想像を超える料理で、とてもじゃないが、甲乙付け難い。
「どうされます? 妖木妃様……?」ムッシュがそう問いかけた。
「ハッキリ言って、どれもが凄い料理で身共たちでは決めかねますな」白陰もそう言って、頭を抱える。
すると妖木妃は思い立ったように、助手妖怪たちに料理を集まった妖怪たち全員に配るよう命じた。
「ワシたちだけでは、とても判断できん。そこで、今……この対決を見ていたお前らにも、判断をしてもらうことにした!」
妖木妃はそう言って、今見ている妖怪を指差した。そう……彼女が指定したのは、今見ている妖怪。つまり、貴方だ!!
貴方にも、審査に加わってもらいたい!
…ということで、BADENDルートの物語は、ここで中断です。
| 妖魔狩人 若三毛凛 if | 11:10 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑


